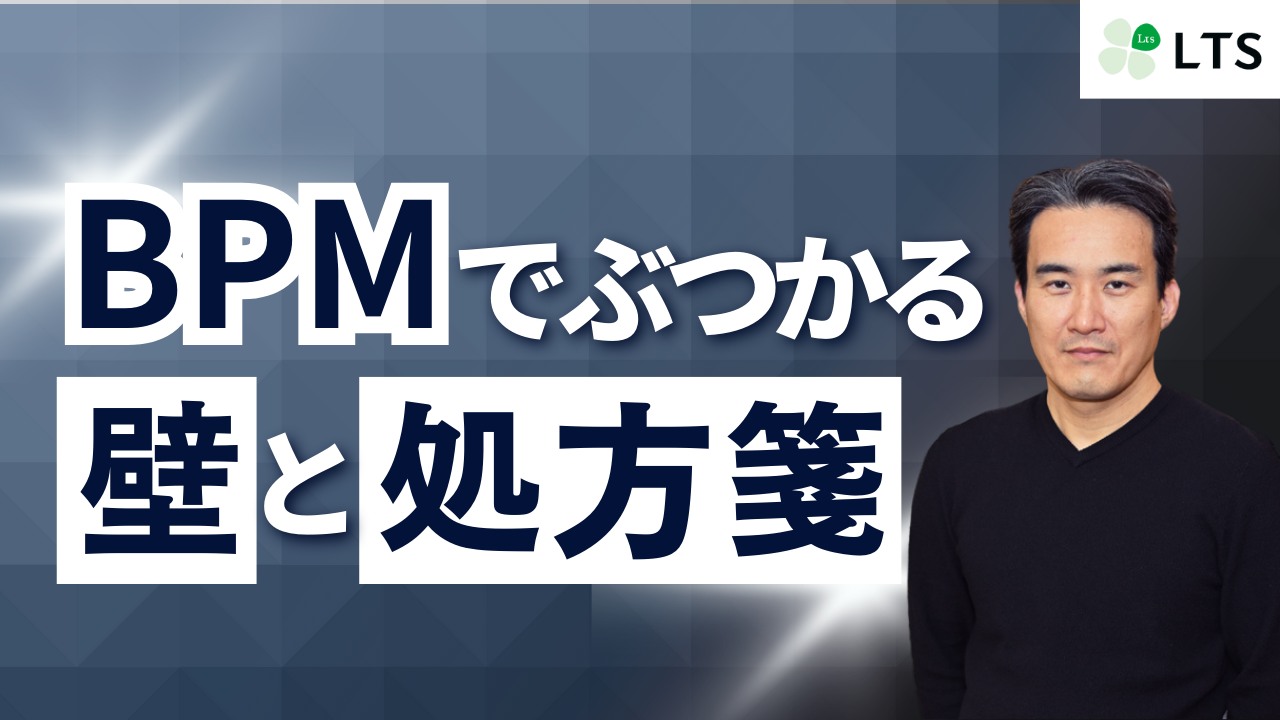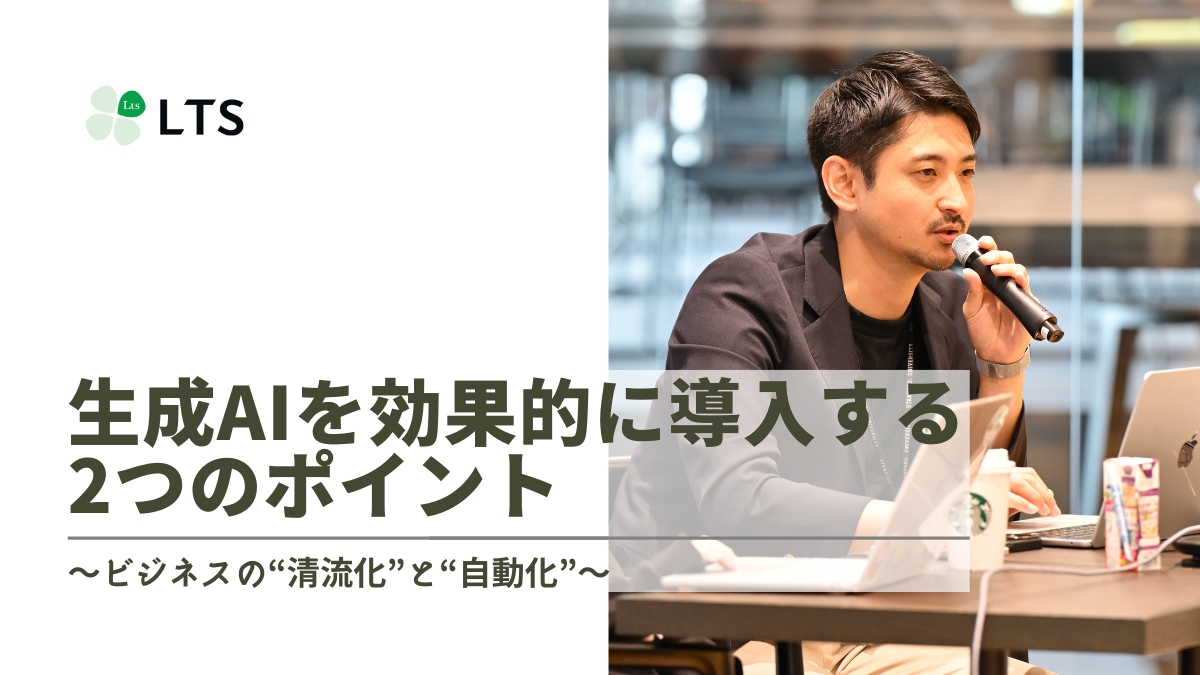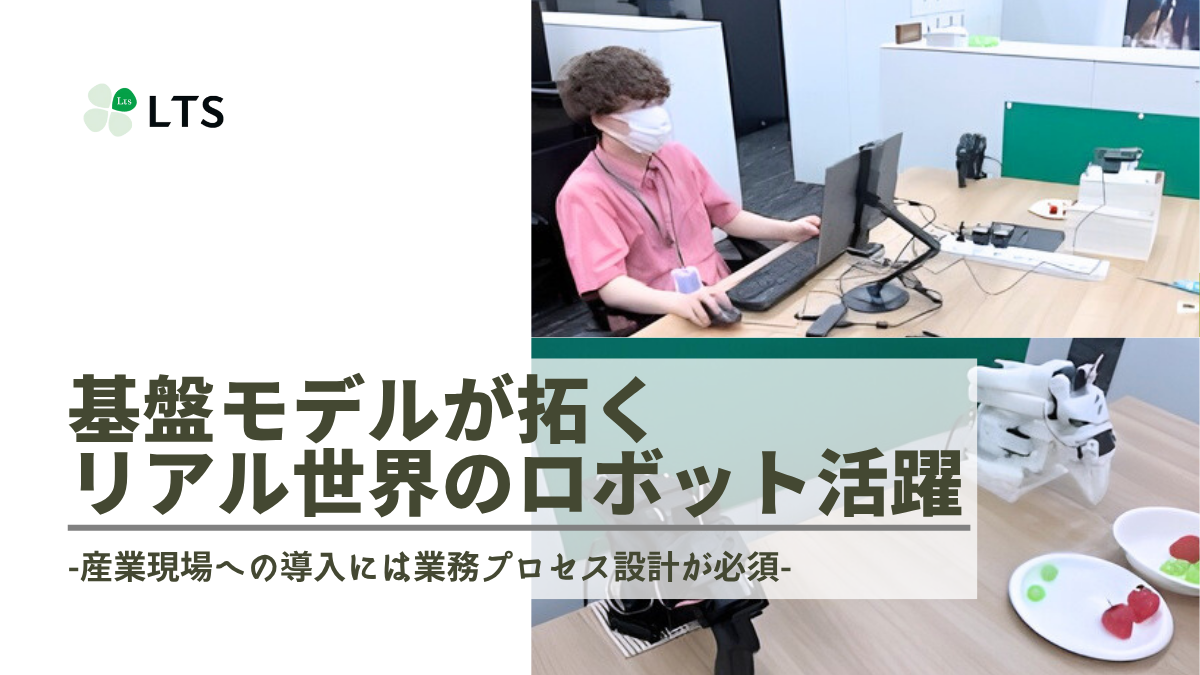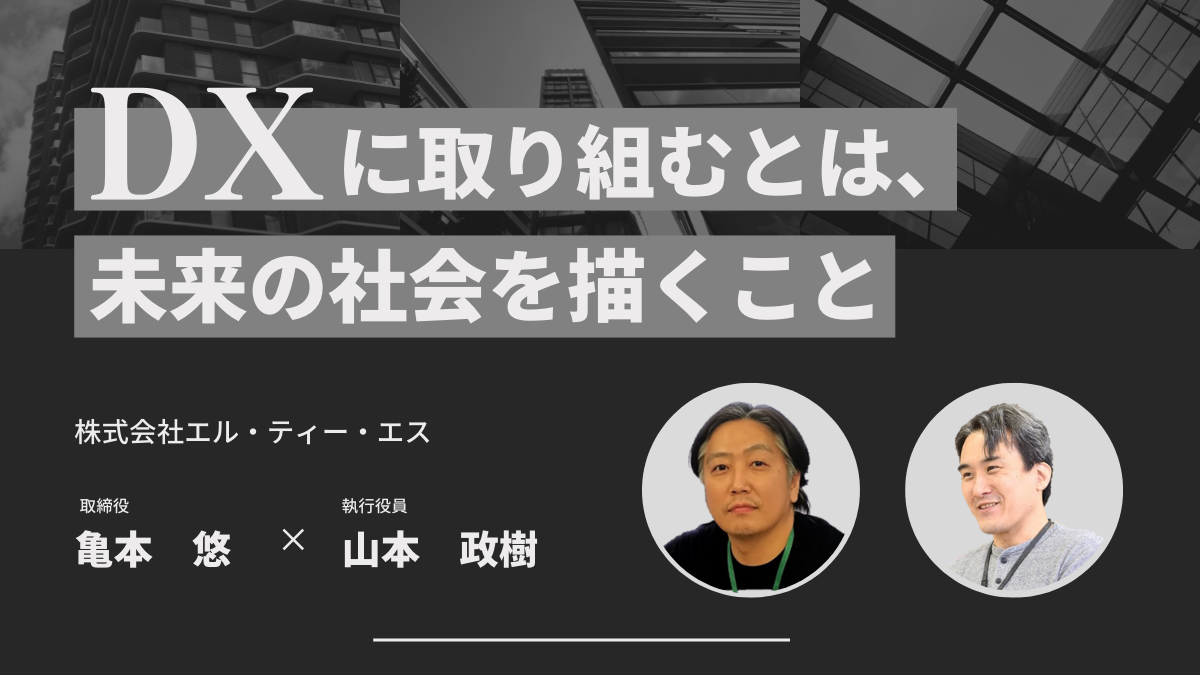「運営するIT部門から経営するIT部門へ」―。ITを使わないビジネスはあり得ない現代、一方でコストが増大する、成果を測定できない、コスト情報抽出の手間が大きいといった課題を抱える企業、担当者の悩みが聞かれます。グローバル企業はITファイナンス高度化へどんな取り組みをしているのでしょうか。LTSが伴走している横河電機株式会社のデジタル戦略本部IT企画センター長・黒﨑裕之氏と、シスメックス株式会社のDX戦略推進本部デジタル企画部長・内藤貴道氏に対談して頂きました。お二方は「カギは可視化と方法論。全社の情報を有機的に結びつけること」と指摘します。
対談は2025年1月、東京都港区のLTS本社で行われました。ファシリテータ―は、LTS Consulting事業本部の畑浩之と若林勇太です
プレスリリース<LTS、ITファイナンスの高度化支援サービスを本格開始>

SIerを経てLTSに参画。大手生命保険会社グループのIT戦略の立案、ITアーキテクチャ設計をプロジェクトマネージャーとして多数経験。LTS参画後は高度なITを活用した戦略検討に加え、企業の持続的な価値創出に向けたIT組織能力向上の観点からITガバナンス・ファイナンスを通じて企業変革を支援している。(2025年1月時点)

LTS入社後、自動車メーカーのIT部門においてBPOサイト責任者を経験し、ITコストの最適化を実現。様々な業界・部門を対象にITファイナンス・BPM(ビジネスプロセスマネジメント)の考え方の導入を推進してきた。(2025年1月時点)
資産からコストに クラウド時代の変化
―――(LTS畑)両社様ともTBMを導入しています。背景や課題をお願いします。
TBM(Technology Business Management) Apptio, Inc(https://www.apptio.com/)の Sunny Gupta氏が提唱した、IT部門リーダーのための方法論。「継続的なビジネスインパクトをもたらす事業経営のために、テクノロジーの経営資源(ヒト・モノ・カネ)と投資ニーズを統合的にマネジメントし、IT価値最大化を実践するベストプラクティス」と定義されている。IT部門に関わる投資や効果などデータを可視化し、ITリソースの適切な調整、IT投資予算の最適化などを実現することが目的。

内藤 横河電機さんが先を進んでおられますがシスメックスの場合、ERPの刷新にあたり、「業務プロセスの再構築」というミッションがトップから下されたのが18年秋でした。それから6年、様々なデジタル化の投資を行いました。そこで投資効果を最大限にするために、まず投資の可視化が必要と認識しました。我流ではなかなか上手くいかず、さまざま検討した結果、グローバルに適用できるTBMに行きつき、LTSに相談したのがきっかけです。
このようにIT投資効果を最大化したい、という課題から出発しています。LTSの「ITファイナンスの高度化は経営に資する」という提案が響きました。

―――(LTS若林)シスメックス様のIT投資計画を見ていくと、IT部門で把握できていないIT投資(業務部門の予算で実施したIT投資)があり、全体を把握できていないことが大きな課題の一つだと気づきました。変革(TX)投資にどれだけ予算を振り向けられるのか把握することが重要なテーマであり、TBMがその解決の手段になり得ると認識しました。
LTSはシスメックス様へのTBM導入にあたり、実際の状況に合わせたユースケースを策定し、実現に向けた独自のレポート構成を提案しました。この際、ライセンス費用が高額になりやすい既存のSaaSソリューションは使用せず、データの分析や情報共有を行うMS社のPower BIでレポートを作成。TBM導入におけるコスト分配方法など疑問解消のための討議会を実施するなどしました。
内藤 そうですね。DXブームによりIT投資が大きくなってきたことに加え、オンプレミスからクラウドに比重が変わってきたことで、 P/Lに直接響くようになりました。ITの重要性が増したことで、IT投資に対する考え方、価値観が大きく変わった(パラダイムがシフトした)と感じています。

―――(LTS若林)ご指摘の通り、現在のIT投資はオンプレミスの自社資産になるのではなく、クラウド・SaaS利用料というコストが増える傾向にあり、クラウド費用をどう下げるか課題ですね。
黒﨑 横河電機ではクラウド化を進めています。ITのアジリティ(俊敏性)を獲得する狙いと、ITインフラによる環境負荷を下げ環境情報開示、ESG開示に備えるという目的もあります。
一方、クラウド化の推進により、そのコストは数倍に上がっていますし、今後もクラウド化は継続します。コストを抑えるためにグローバルで契約を一本化してディスカウントを求め、可視化ツールで利用状況、トレンドを把握しています。使っていないものは解約・リサイズ・随時利用(必要な時のみ稼動)するように取り組んでいます。

―――(LTS畑)コストを抑えるのに必要なことは何ですか?
黒﨑 グローバルITガバナンス、例えば、Delegation of Authority(権限移譲)の明確化、グローバル人事管理の導入と実践、そして経営意思決定と多岐にわたります。そのためにRACIチャート(プロジェクト管理でタスクに関与する人や役割、責任を明確にした表)を整備しています。ユニバーサルサービスはすべて本社で契約や管理を担っていますが、全社に無駄のない効率的な理解を進めるにはやはり方法論が必要です。そこでTBMを導入しました。TBMがなければ本当の意味でのIT化はできないと感じています。
―――(LTS畑)横河電機様はTBMによるグローバルなプロセス構築・ガバナンス確立に時間をかけて取り組まれていますよね。グローバルの誰もが理解できるフレームワークが重要だと思います。一方、TBM導入の課題はありますか。
連邦型ではグローバルに通用しない

黒﨑 なにより、「グローバルメンバー全員が理解できる」ことがキーワードかと思います。方法論無しではオペレーションできませんから、大切なのはルール・知識・仕組みであり、TBMが適していると感じます。自分たち(本社)が良いと思っている方法論でもグローバル、各地域ではそうではないということがあります。
―――(LTS若林)共通の方法論、言葉を持つにはTBMが良いということですね。シスメックス様はこれから本格的にTBMの導入ですね。
内藤 ファイナンス領域では会計基準がグローバルの共通言語となっているように、IT領域ではTBMがIT投資管理のグローバルの共通言語となることを期待しています。フレームワークを導入することによって、スタートラインに立てたというのが大きいと感じています。
黒﨑 横河電機もTBMでオペレーションできるか今、取り組んでいるところです。多くの会社において、ITガバナンスは地域連邦型か中央集権型かを選択されます。地域連邦型の場合は一部が「自分が一番」と考えて個別最適に行動し、ガバナンスが効き難くなるところが難しい点です。情報や投資などを一元管理するアドミン組織のグローバル化が大事ではないかと感じています。
―――(LTS畑)グローバル展開する企業ならではの、ITガバナンス確立の悩みはありますか。
黒﨑 外資系企業、例えば、ボッシュさんはグローバルプロセスオーナー制を敷いているとうかがったことがあります。横河電機でもそのようにしています。苦労はあるものの、妥協してはいけないのは全体最適な視点でITを管理していくことだと考えています。
内藤 シスメックスグループでは、ERPの刷新に合わせてSAPのビジネスシナリオ(ベストプラクティス)をベースに、業務プロセスのグローバル標準化を行いました。グローバル標準のプロセスオーナーには、日本人以外の者もいますが、現時点では地域から本社へのレポート体制が構築できていません。グローバル標準プロセスの維持統制のため、CoE(Center of Excellence)体制の確立に向けて組織づくりを進めています。
HR、環境対応も迫られる

―――(LTS畑)世界各地に駐在するプロセスオーナーは、現地採用の人たちですか。
内藤 現在のところはそのとおりです。シスメックスグループでは職務型のグローバル人事制度の導入と同時に人事システムをグローバルに統一しました。日本では従来、メンバーシップ型の人事制度でしたが、新しい人事制度により、管理職以上のポジションには職務記述書を用意しました。今後は、グローバルに統一した人事制度とシステムを活用し、地域を横断した人材の交流が進むことを期待しています。
黒﨑 例えば、横河電機の中東のIT部隊では現地(中東アフリカ)の仕事の効率化により、グローバルIT業務も遂行しています。このように、グローバルITの仕事をする人は世界各地に分散していて、その点で人事制度の設計を工夫しています。
―――(LTS若林)IT部門の業務には予算の管理もありますが、IT戦略を担うので経理部門とは視点が違いますね。
黒﨑 そうですね。例えば、収益に対するクラウドコストを説明する必要があります。ここでカギになるのは可視化、リソースに対するタギング(各クラウドコストを分類分けしてタグ付けをすること)です。地味な仕事ですが非常に重要で、これが機能しないと上手くいきません。弊社では、この領域にApptio社のCloudabilityを利用しています。
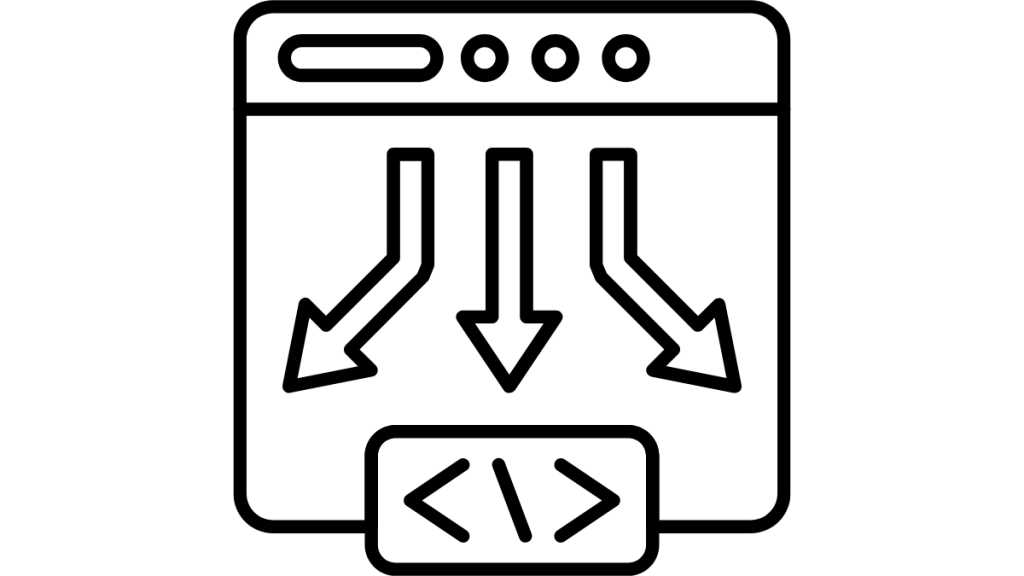
内藤 ERP刷新など社内ITを10年ほど担当してきましたが、時代は大きく変わりました。昔のIT部門はファシリティ管理のように、ITシステムの維持運用管理が中心の仕事でしたが、現在は戦略策定にも関わるようになりました。予算にまつわる業務も多岐にわたります。クラウドやノーコード/ローコード開発が増え、IT部門への期待や役割が変わりつつあります。
戦略的なIT投資により経営に貢献することが期待されていると感じており、ITファイナンスの高度化によるIT投資の可視化、変革への投資拡大などが重要になると考えています。
※
LTSは、10年以上にわたるITファイナンスの企画・運用により蓄積された豊富な実務知見、お客様の現状を踏まえた長期的・伴走的な視点で、ITファイナンスの高度化に向けた複数年の計画構想、お客様の自走サポートを提供しています。
具体的には、ITコストに関わる業務プロセスやデータ管理方法を把握し、問題の真因を特定するとともに、お客様の検討論点を早期に明確化。伴走型の支援により、お客様自身のITファイナンスのリテラシーを向上し外部に頼らない自立を目指します。また、お客様に合わせてテーラリングするTBM適用も支援します。
ITファイナンス高度化は、自社ですべて実現するには限界があります。そこでLTSでは、グローバルなTBMのコミュニティでの議論にも取り組んでいます。日本ではまだ普及していませんが横河電機、シスメックス両社様への支援をきっかけにコミュニティやネットワークを成長させたいと考えています。
エディター・ライター

新聞記者、月刊誌編集者を経て2024年1月にLTS入社。北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニットを修了し、同大でサイエンス・ライティング講師を経験。著書、共著、編著に「頭脳対決! 棋士vs.コンピュータ」(新潮文庫)など。SF好き。お勧めは「星を継ぐもの」「宇宙の戦士」「ハーモニー」など。(2024年1月時点)