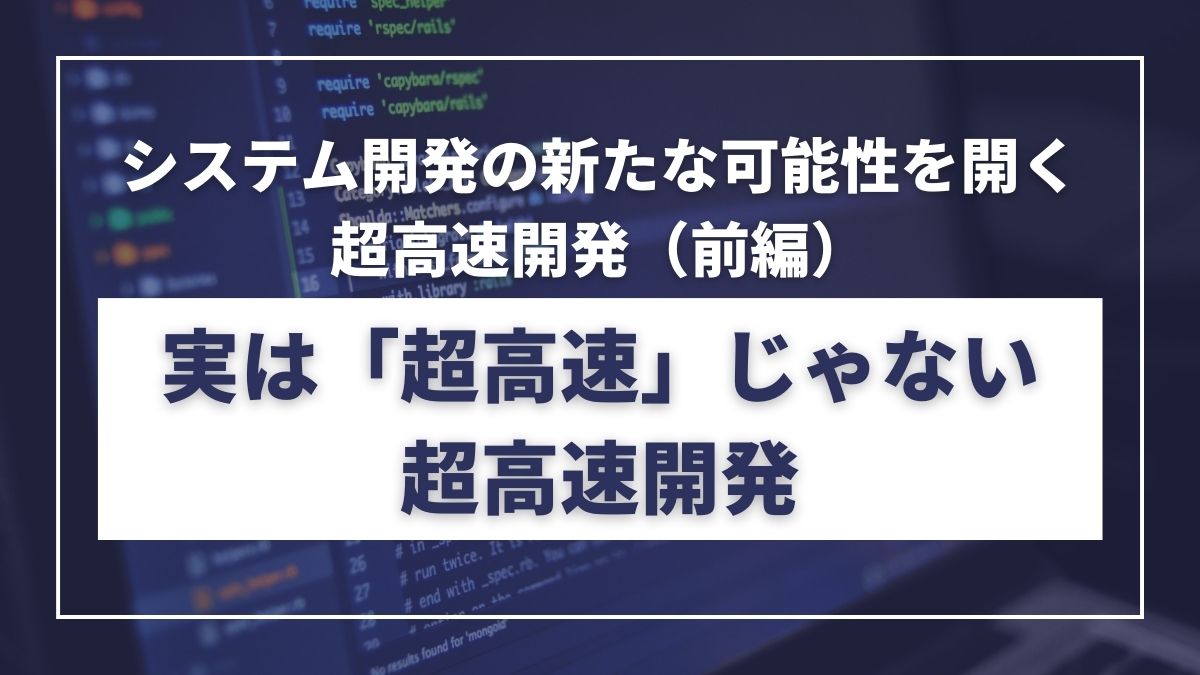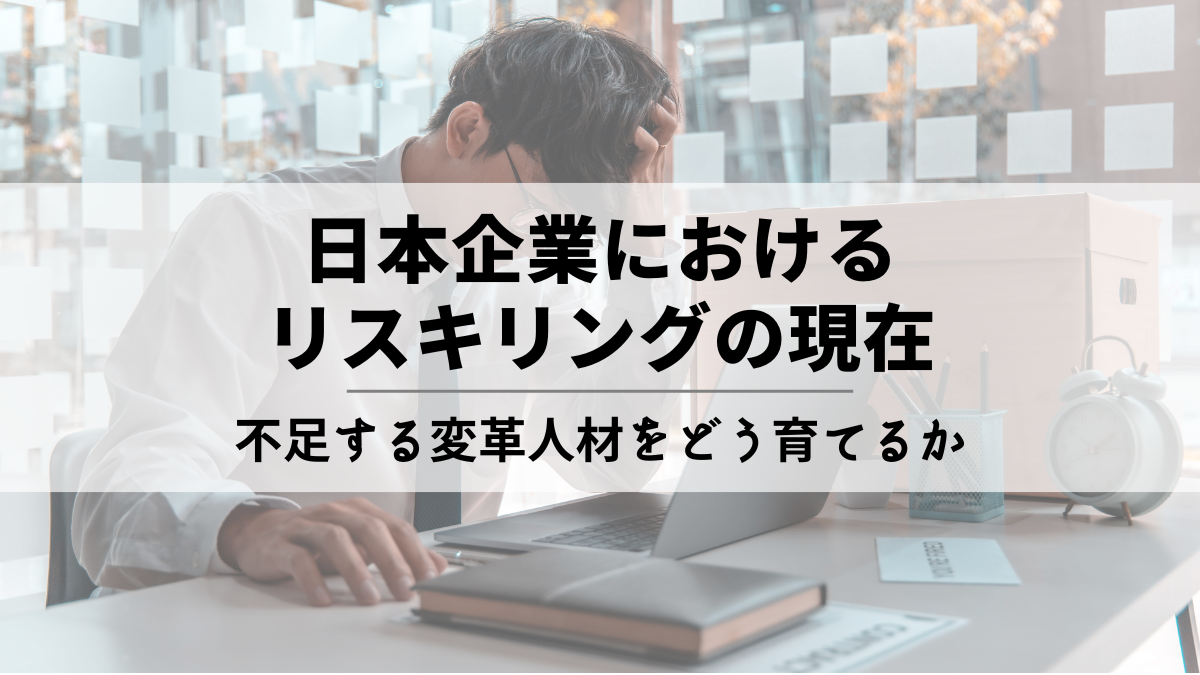デジタル・テクノロジーの進化が著しい時代の経営戦略とは? そもそも現代に戦略は必要なのか?―。LTSは2025年、市場・産業調査、M&A実行・企業間アライアンス支援などを担う戦略コンサルティング事業本部を新設しました。常務執行役員CSOの山本政樹と同事業本部長、亀本悠が重ねた議論を3回に分けてお伝えします。(上)のテーマは<「戦略」を再考する 歴史は繰り返さないが…>です。
プレスリリース https://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-02-07
※LTSは「デジタル時代のビジネス変革」を再構築するため、山本がファシリテーターとなり、LTSのリーダーと議論を重ねています。議論の成果は2026年に出版予定です。
デジタル優位でも不変の資質
山本:
LTSは今年、戦略コンサルティング事業本部を新設しました。そもそも亀本さんは〝戦略コンサルタント〟をどう捉えていますか。

亀本:
ちょうど先日のことです。ある会合で大手製造企業がBPO(Business Process Outsourcing)などを手掛ける会社と、間接業務を担う子会社(JV)を設立したことが話題となり「なぜこのような手法がとられたのか?」と、経営者の方から質問を受けました。
BPOにはコスト最適化やDX/標準化、投資/リスク分担といった目的があります。現在、BPOは労働集約型からデジタルプラットフォーム型に移行しつつあり、BPO事業者としては「作業を請け負う会社」から「成果を共同で創出するパートナー」モデルに転換する状況にあります。質問を受けたケースはシェアードサービスとのハイブリッド型で、JVによる5-10年スパンでの超長期コミットによるリカーリング(継続的)収益の確保といったメリットを生かすことで、単価下落といった従来型モデルを打破し、アップサイドリスク(成長余地)を共有するというJV設立の意図を説明しました。
山本:
一口にBPOといっても、時代によって役割や機能、形態も変化していますね。単純な委託・受託の関係では捉えられないですね。
亀本:
はい。現在までの時間軸で起こった外部・内部環境の変化を捉え、複数の選択肢を踏まえた結果、そうした意思決定をした―というロジックです。これを語れるかどうかが戦略コンサルの腕の見せどころだと考えています。
私はコンサルティングをする際、PEST分析(Politics=政治、Economics=経済、社会Society=社会、Technology=技術の観点から外部環境を分析するフレームワーク)を用いることがあります。その際にも、時間軸を基にした情報は非常に重要だと考えています。

山本:
時間軸の情報とは、いつ、どの企業に、どういった経緯で、何が起きたのか、またそれぞれの因果・相関関係といった歴史的文脈、コンテクストということですよね。マーク・トウェインは「歴史は繰り返さないが韻を踏む」と言いました。やはり、確実性の高い戦略を立てるためには、過去の歴史を知ることが重要だということでしょうか?
亀本:
はい。戦略コンサルは、あらゆるファクトやデータから見た歴史を基に、現在をさまざまな角度から理解しようと努めます。冒頭で紹介した企業のJV設立のような「すでに起こった未来」(※1)を理解するには、どのようなテクノロジーが生まれ、どのようなレギュレーション(規制)があり、どのような環境変化により事業が歴史的に変化してきたのか―を分析することが重要だと考えています。ですから私は、後輩に「戦略コンサルであるために何をしたらよいのか?」と問われた時、「歴史家であれ」と言ってきました。
※1 ピーター・F・ドラッカーの論文集「すでに起こった未来」(ダイヤモンド社)。
山本:
私はいま、LTSのビジネスリーダーたちと、「デジタル時代のビジネス変革」をテーマに議論を重ねています。デジタル・テクノロジーの進化が著しい現在は、変化のスピードが激しく、過去の情報から将来を予測することの難しさもあります。その意味で、戦略論を考える上での歴史的な転換点に私たちはいるとも感じますが、亀本さんはこのような状況をどう見ていますか?
亀本:
歴史的に大きな転換点にあることについてまったく同感です。しかし、デジタル優位な時代でも、戦略コンサルに歴史認識、原理原則と教養が求められることは変わりません。伝統芸能や音楽など芸術には必ず原理原則があり、理解にはそれを知ることが必要です。同様にテクノロジーを理解するにも原理原則を知っておく必要があります。
戦略コンサルは「なぜそうなるのか」を根本から理解した上で、お客様をサポートしなければなりません。それがなければ、ただのテクノロジー活用方針になってしまいます。テクノロジーの使い方やマーケットの捉え方について原理原則、歴史的認識を含めた支援ができないのであれば、戦略コンサルは不要という危機感があります。
DeepSeek登場は予見できた⁉
山本:
激しく変化しているように見える環境でも、その裏側には歴史的経緯から生じる原理原則が生き続けているということでしょうか。テクノロジーは現在、その進歩に比例してすべてを追いかけることが非常に難しくなっていますが、原理原則を理解していることがどのようにテクノロジーの進歩を追うことにつながるのか、もう少し詳しく解説していただけますか?
亀本:
テクノロジーと戦略の関係は後述するとして、逆説的ですがテクノロジーへの感度を上げるにも、原理原則を知ることが大切です。中国のDeepSeekが好例です。 アカデミアの世界では、生成AI開発で、ある共通認識がありました。それは、いずれ中国が優位に立つだろうということです。

高性能の生成AI開発には質の高いデータが必要です。日本、欧米と異なり中国では個人情報などを集めやすいことは、よく指摘されることです。さらに重要なのは、4000年の歴史で蓄積された文献の価値です。漢文は同じ意味でも文脈によって異なる表現があり、込められている感情や意味は細分化しています。学習データとしての価値が高いのです。以前からアカデミアの方たちと「中国には勝てないかもしれない」と議論していました。
山本:
中国でDeepSeekが開発されたことは、起こるべくして起こったということでしょうか。
亀本:
その通りです。原理原則を理解している歴史家、戦略コンサルであれば、DeepSeekのようなものが中国から誕生することは、ある程度予測はできていたはずです。

「起こった未来」を積み重ねる
山本:
ここまでの話をまとめて、改めて亀本さんなりの〝戦略〟を定義すると、どう表現できますか。
亀本:
一言で示すなら、「『すでに起こった未来』の積み重ね」です。「起こった未来」が今後どう影響するかは誰にもわかりません。しかし、過去の事象への対応とその成績や結果は3年前、5年前、10年前…とそれぞれの時系列に存在しています。数字で見える範囲は限られるものの、この点については評価分析が可能です。「起こった未来」を評価分析し積み重ねることが〝戦略〟ではないでしょうか。
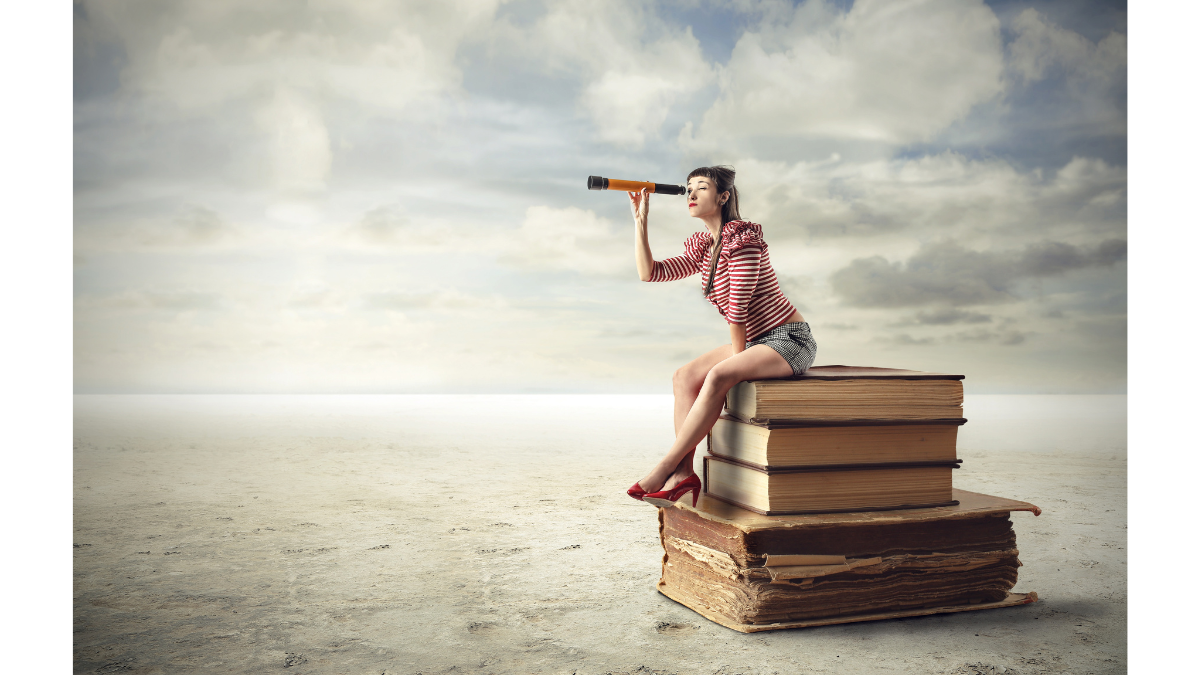
山本:
「起こった未来」を評価分析し積み重ねること、つまり過去から繋がっている現在状況と、未来に起こり得ることを俯瞰し外部環境の変化を踏まえた時、企業が現実に取りうるシナリオは絞られますよね。
亀本:
はい。例えば、ある業界で大きなインパクトになり得る事象が起こるとします。ある会社は事業縮小を検討し、別の会社は競合の事業縮小を予想して資源を投入するかもしれません。事象に対する反応はそれぞれ異なりますが、過去にどんな選択をしてきたかを見ると少なくとも選択しうるシナリオは絞られてきます。これがドラッカーの言う「未来のことは予測できないが、すでに起こってしまった未来を探せ」、つまり予測できない未来を予測する、ということではないでしょう。
山本:
「すでに起こった未来」により絞られた外部環境と自社、それぞれの選択肢を照らし合わせた時に現れるだろう複数のシナリオのうち、最終的にどれに投資していくかは決断力の問題となるのかもしれません。しかし、その前に少なくとも「明らかなハズレ」は消すことができるということですよね。

亀本:
確度の高いところを見定めて、取り得るシナリオから自社の進む道を決める、そしてそこに資源を集中させる。この一連のシナリオ・プランニングが戦略立案です。戦略コンサルティング・サービスの究極のゴールは、限りある経営アセットの分配方針に対するアドバイスですよね。
山本:
特にデジタル時代にこそ、限りある経営アセットをどう分配するかが重要ですよね。つまり、戦略という土台なしに目標を語ることはできません。先日、あるお客様とお会いした時のことです。お客様が、戦略のない状態で業績目標を作ろうとしていることを知り「それは違う」と少し激しい議論になりました。
リチャード・P・ルメルト(戦略論の第一人者として知られるアメリカの経営学者。マイケル・ポーターなどと並ぶ戦略論の重要人物)の「戦略があって初めて目標がある」という言葉が示すように、業績目標は戦略シナリオを定めて設定されるべきだと私は考えています。
一方、テクノロジー進化という文脈から、現代は戦略に対して2つの否定的問いかけもあると感じています。「戦略は現代のような変化の速いテクノロジー時代に本当に役立つのか」「戦略立案は事業を創造するイノベーションに逆行するのではないか」という問いです。
エディター・ライター
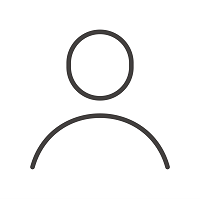
2021年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味は旅行、食事、犬猫動画を漁ること。(2024年6月現在)