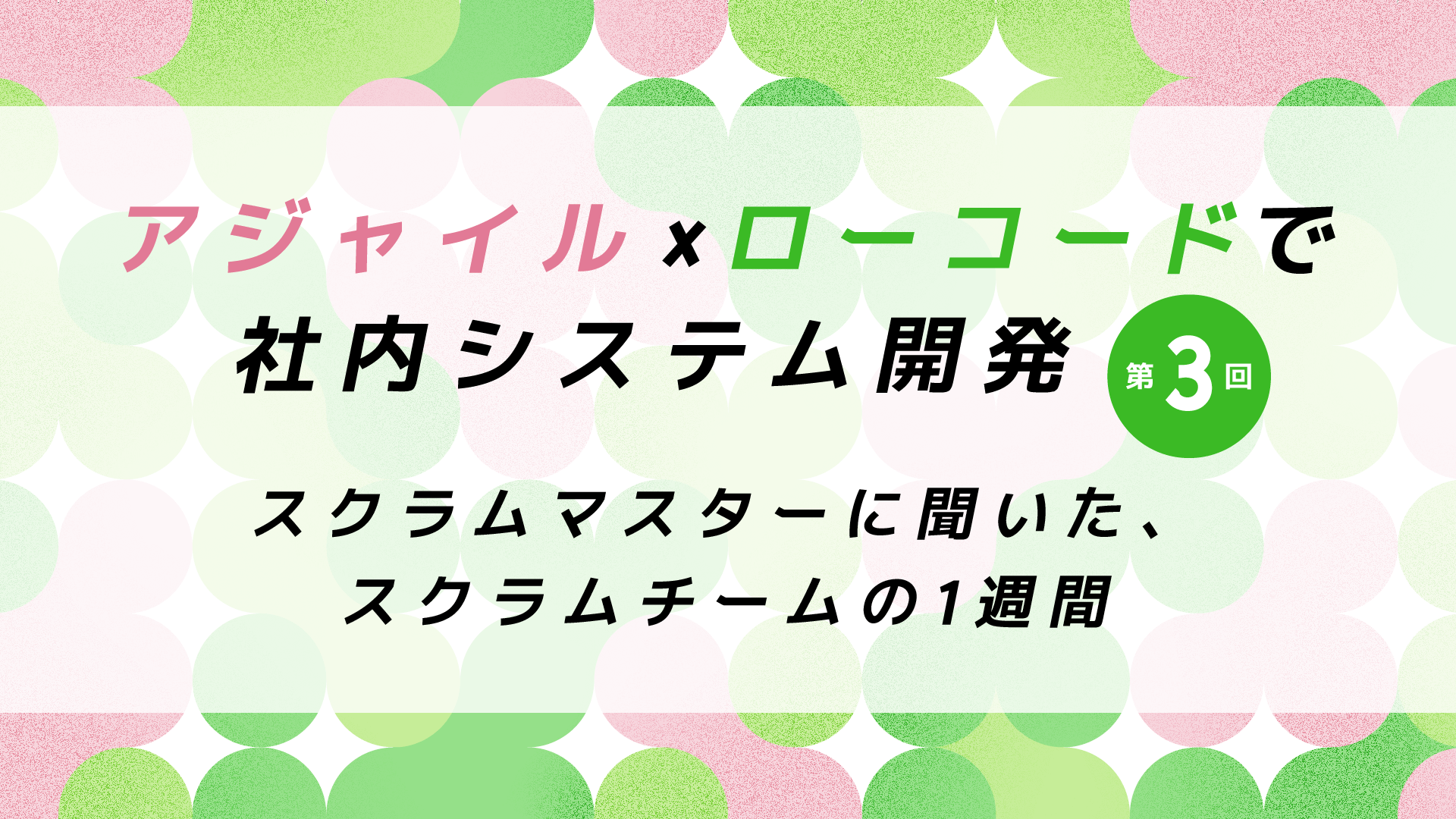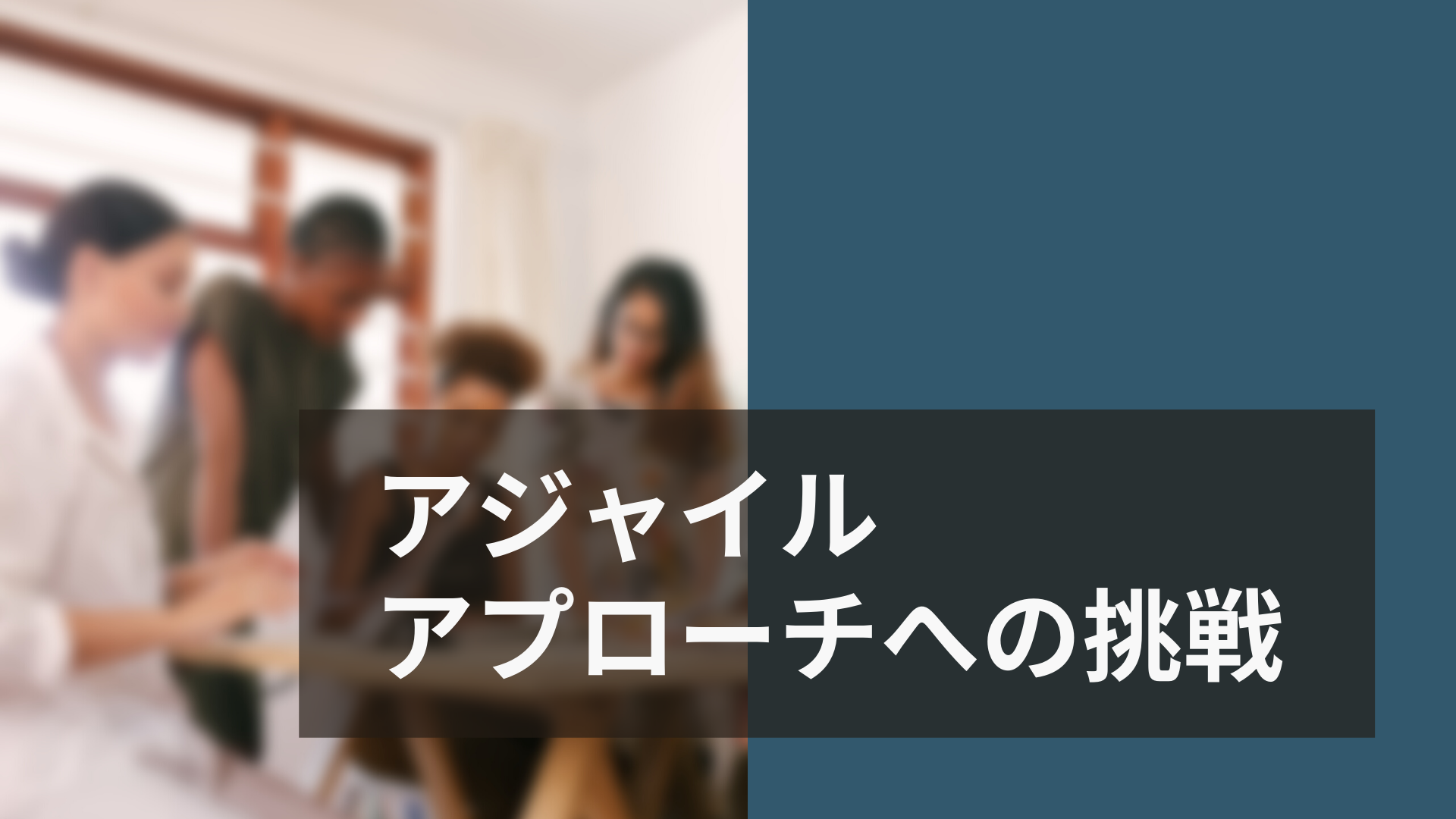※議論の成果は2026年に出版予定です。
芯がないままプロジェクト始動
山本:
髙橋さんはEnterprise Transformation事業本部本部長としてERP領域を統括しています。ERP導入や刷新が難航するプロジェクト(PJ)には、どんな課題があるのでしょう。
髙橋:
しばしば聞くのは、SAPのようなERP導入に際して、いわゆるFit to standard(F2S、システムに業務プロセスを合わせる手法)で導入しようとPJが始動したものの、現場の理解を得ることができず結局、旧来型のカスタマイズやアドオンを多用した開発に回帰してしまうというケースです。これは、ERP導入の目的やF2Sの本質的な狙いや効果を明確にせずに、ビジョンがないままPJを進めてしまうことが原因です。
企業の変革ビジョンを描けていないまま「202X年の崖だから」「他社が ERPを採用しているから」との焦りがPJの原動力となっています。 経営が企業変革に対する芯を持っておらず、現場の課題を吸い上げて取り組もうとするので、結果としてPJは大規模化、複雑化し難易度が上がり失敗するリスクを高めています。

山本:
ERPの刷新や導入には膨大な費用・工数がかかるので、顧客にも大きな負荷がかかると思います。とは言えなぜ、ビジョンが不明確なままPJが始動してしまうのでしょう。
髙橋:
まさに202X年の崖に関連してEOSL (End of Service Life、サポートや保守の終了)の影響が大きいですね。既存システムの保守期限切れのタイミングで、「これを機に、ERPを導入しよう(刷新しよう)」と考える企業は多いのです。ERPは変革のスタート、企業の未来を支えるものですから、本来はこの段階でビジョンを検討するべきなのです。しかし「単なる業務システムの導入・刷新」というレベルの取り組みとみなされてしまうことで、そもそもビジョンの必要性を感じていないということがあります。仮にビジョンの必要性を認識していても、EOSLの期限ギリギリで取り組みに火が付くので、結局足元にフォーカスされてしまい、ビジョンが十分に議論されないままスタートせざるを得ないという状況もよく見かけます。
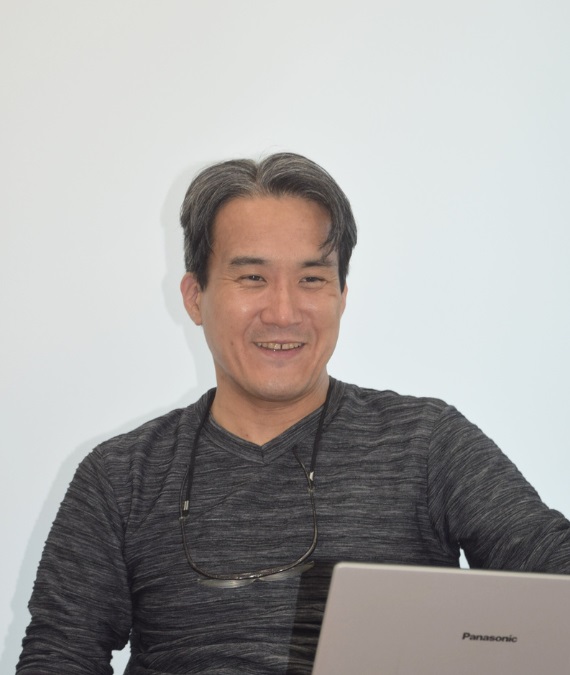
山本:
髙橋さんが言う「PJの芯の喪失」というようなものが、混乱を起こしているのは確かですね。また現場レベルで言えば、情報システム部門など、かつてのレガシーシステム開発、ウォーターフォール全盛時代に活躍した“オールドデジタル人材〟との折衝も難しいものですね。
髙橋:
はい。PJマネジメントにおける本来の品質管理とは、顧客からの要求を反映させ、ツールの利便性を向上させるための取り組みです。ただ、情シス部門が欠陥防止やレビューテストに重きを置く旧来型の品質管理にこだわってしまうと、アジャイルな進め方ができずにPJのボトルネックになりかねません。
社長インタビューができない
山本:
オールドデジタル人材にももちろん、彼らなりに「バリューを発揮しなければいけない」という責任感があると思います。ただ、重箱の隅をつついて穴を探すばかりだと、PJが停滞しますね。
いずれにしても、これら課題について経営陣の責任は大きいと思います。というのも、経営陣がERPを「現場を効率化するためのシステム」としか捉えないので、現場もERPが企業変革の一端を担うシステムではなく、目先のメリットを享受するためのツール、としか認識しないのです。
髙橋:
はい。私が担当したあるPJでは、経営者との議論をお願いしましたが、お客様PMに断られたことがあります。「ERP導入に社長インタビューは不要」とのことで、これは非常に残念でした。現場を責める意図ではなく、やはり根底には最終決定権を有するトップのERPへの誤認識があるように感じます。実際にトップからは現場の利便性とコストに関するコメントをいただくことが多いです。トップが五年後、十年後の長期的な企業のビジョンを掲げ、「なぜERPが必要なのか」を根気強く説明し、全社員、ステークホルダーのベクトルを合わせなくてはなりません。

企業が提供する価値の源泉は何か
山本:
長期的な企業のビジョンを掲げるためには、経営陣の経営管理指標への考え方もバランスがとれたものにしていく必要があります。現在はP/Lを評価対象とする企業が多数です。しかし、P/Lを見ているだけでは、目先の改善を繰り返すばかりになります。大きな変革を現実にするためには、「あるべき姿から見るべき数字=変革に向けた進捗」をこそ追うべきなのですが、そもそも「見るべき数字が何か分からない」という経営者が多いのではないでしょうか。
髙橋:
はい、そういったご相談もよくいただきます。「見るべき数字」というのは戦略目標を定量的に表現したものですから、それが分からないというのは、自社の戦略目標自体がクリアになっていないことを意味しています。先ほどから話に上がっているビジョンが不明確ということと同義でしょう。ちなみに、短期で見るべき数字は、例えば各サービス/製品×市場の単位で売上・利益構成などの数字を可視化することで、「何を」、「どこへ」売ったのか、利益効率がよいのか、などの情報がクリアになり、人・組織を動かす意思決定に役立てることができます。そしてこの足元の数字の信頼性を高めるためには業務プロセスや業務ルールの標準化が重要で、効率よくデータを収集する基盤としてERPが活用されるわけです。
山本:
強調したいのは、ERPは目先の効率化ツールではなく、迅速で長期レンジの戦略を構築するための基盤ということですよね。
髙橋:
はい。長期的なビジョンを議論できるようにするためにも、現状のビジネスの実態を精度の高い数字で表現できる業務プロセスとERPのようなシステム基盤を整備することが重要です。長期の視点では、価値の源泉がより一層無形固定資産に移ってきている中で、おっしゃる通りP/L以外の指標にも目を向けるべきです。変革人財の育成が至る所でテーマに上がっているのは、まさに企業の中長期の成長の源泉が変革人財にかかっていると捉えているからです。その意味では人材戦略の進捗状況は「中長期での見るべき数字」の一つとしてしっかり追っていき未来に向けたアクションに紐づけるべきです。

非デジタルとビジネスの深淵
山本:
現状が正しく認識されないと、あるべき姿とのギャップが把握できず、正しいアクションに繋がらないですよね。また、数字を見る際にも注意するべきことがありますよね。数字そのものを追うのではなく、数字の裏側に潜むロジックまで見つめることです。例えば、「なぜ部門間で数字に差があるのか、それをどう是正していくのか」と提言することが経営者のリクワイメント(必要条件)で、数字にしか興味がない経営者になってはいけないですね。
次に、見るべき数字に加えて、F2Sを進めるに当たっては「何を企業の武器にすべきか」というコア(=競争力に資する部分)・ノンコア(=競争力に資さない部分)の切り分けも重要です。ただしこれは、業界によっても異なり、単純な切り分けはできないと思いますがいかがですか。
髙橋:
コアとノンコアの切り分けは業界・企業に加えて、デジタル・非デジタルであるかによっても異なってきます。例えば食品メーカーであれば、コアは差別化された美味しい食料品という非デジタル商品、製造や流通を管理するシステムやバックオフィスはノンコアと置くとします。しかし、ノンコアにエラーや不具合があれば製造や流通が止まり、コアである製品の販売ができなくなってしまいますから、単純な切り分けはできません。
山本:
全国的に有名になったとある菓子店の事例があります。その菓子店は地方のパン屋さんとして順調に経営していたものの、競合の進出で売り上げが鈍化してしまいました。危機感を持った当時の経営者が、菓子領域にシフトチェンジし、東京で大人気の菓子店として再起したのです。

変化する環境と人に目を向ける
髙橋:
パン屋さんから菓子店への転換は、企業にとって大きな変革の実行ですよね。F2Sを進める際に、コアを明確にしてノンコア領域は標準化するという切り分けは、実際に有効です。ただし、コア・ノンコアを無理に切り出すのではなく、企業の大きな変革ビジョンの中でデジタル技術が担う役割を再確認し、コア・ノンコアという表面的な切り分けだけではなく、「自社の競争力を高めるために、自社で意思を持って構築・管理しなければならない領域」を明確に定義しなくてはならないですね。

山本:
はい。コア・ノンコアの相互関係を考慮せず断片的に切り出してしまっては本末転倒です。菓子店のケースを考えると、ビジネスには、コア・ノンコア一方だけではなく、常に双方が円滑に連携していることが前提にあることを示していますね。コアである商品のシフトチェンジは非デジタル領域ですが、背後にはきちんとした製造・流通を管理するシステムがあったのでしょう。
髙橋:
ノンコアに分類されがちな業務を支えるデジタル基盤が整っていなければ、商品やアプリケーションといった売り上げに資するコアは成立しません。ノンコアというと「優先度が低い」「理解しなくて良い」「守り」などと蔑ろにしがちですが、コア・ノンコアの双方ともビジネスの成功に欠かせない要素です。
そう考えると、コア・ノンコアを単純に切り分けすべきではないことも分かります。またデジタル環境によって人・ビジネスのあり方も変化します。ですから、デジタル技術をどう使うかだけでなく、デジタル技術を含めた環境の変化、人の変化にも常に目を向けたいところです。
山本:
そうですね。ここまでERPやF2S導入がなぜ頓挫してしまうか考察しました。現場の反発に関して言うと、DXを成功させるにはステークホルダーの心理的な部分へのアプローチが大切です。これについて(下)で深めましょう。
エディター・ライター
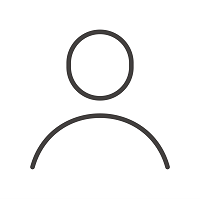
2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)