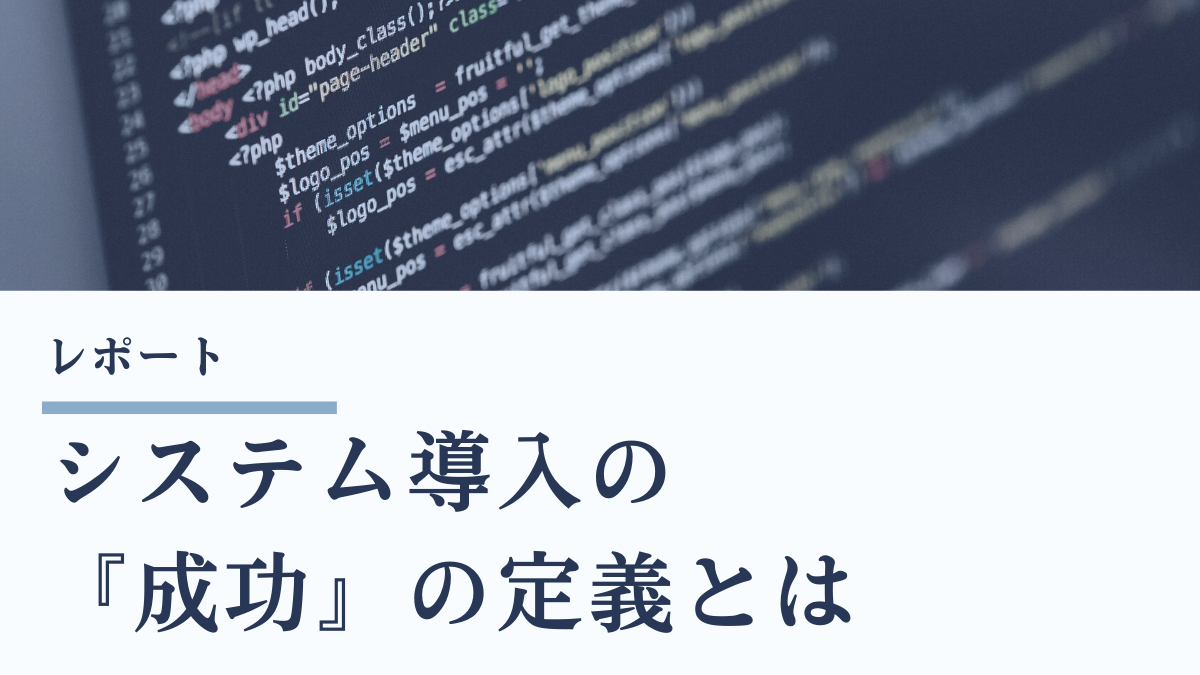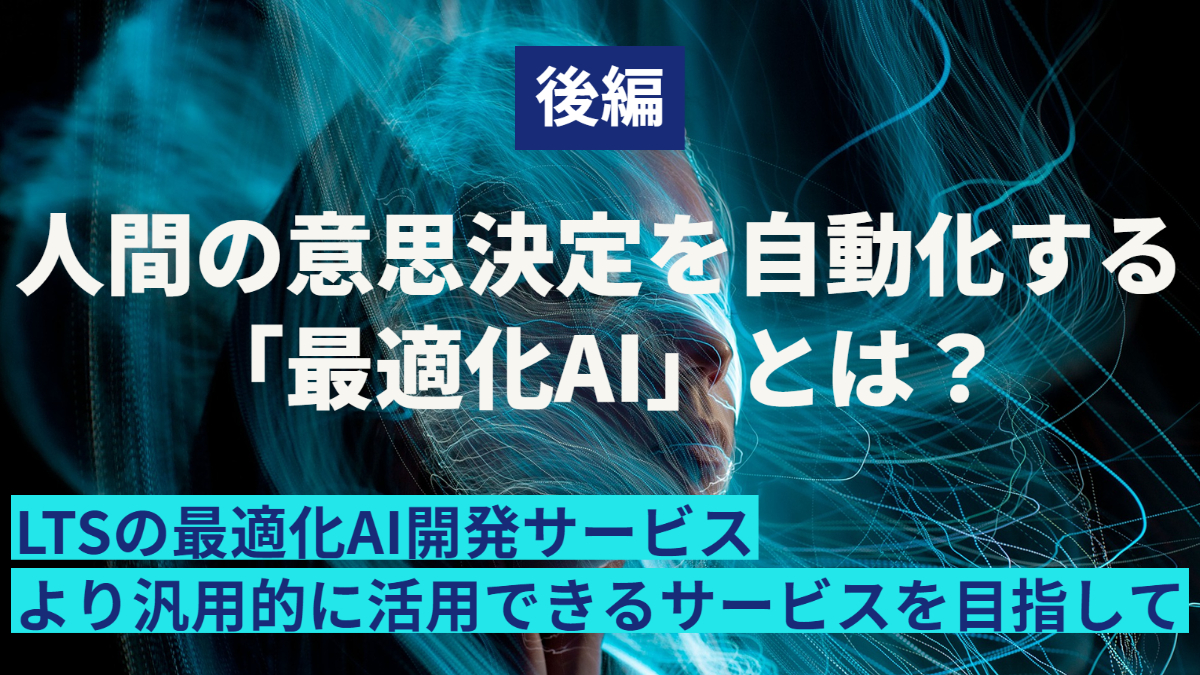※議論の成果は2026年に出版予定です。
心に寄り添うのがコンサル
山本:
DXというと、テクノロジーやソリューション導入といった面に目が行きがちですが、それを使う人、働く人へのアプローチも欠かせません。ERPに関するプロジェクト(PJ)が難航する大きな原因の一つは、ビジョンなきDXを進める経営陣が現場の反発を恐れることだと(上)で指摘がありました。どう克服すべきでしょうか。

髙橋:
大きな変化を起こそうとすると、やはり人間は不安を感じ抵抗を示すものです。ですから、私たちコンサルタントは「なぜ不安なのか、なぜ抵抗するのか」というステークホルダーの心の内面に向き合う必要があります。そして、なぜ今の業務・システムを変えるべきなのかを根気強く説明しなくてはなりません。そうやって現場の抵抗、不安を払拭して、変化を少しずつ受け入れてもらいます。
今の時代は大きな変革の取り組みを終えてからも、次々と新たな変化が発生します。ですので、極端な言い方をすればERP刷新という大きな変化を乗りこえ、その取り組みを通じ変化に対する自信を獲得し、その後も発生する変化に対して顧客自らが変革の主体者となって前向きに取り組めるようになることが、私たちコンサルタントが本質的に向き合うべき課題だと捉えています。
山本:
実は、ユーザーの心理的な側面に寄り添うことは、われわれコンサルタントの重要な役割ですよね。コミットしたPJで、上手くいったケースはありますか。
髙橋:
言葉で言うとすごく単純です。SAP導入PJで、「なぜ新たな仕組みを入れるのか?」「どのように変わっていかなければいけないのか?」を、社長と議論しビデオメッセージを出してもらい、社内報などで定期的に発信をしました。PJの意義・目的を全体周知させることで、全社を巻き込んで、社員が当事者意識を持つきっかけになったと思います。
また、デジタルツールが発展しメール、チャット、オンラインなどで手軽に説明、発信が出来るようになりましたが、反発の大きい部門などには、地方拠点であっても足を運びしっかりと対話をするなど、目の前の効率性にとらわれない考え方も重要だと感じています。

山本:
心理的側面への段階的なアプローチでステークホルダーの支持者を増やし、顧客主体で移行を進めることができたということですね。欧米に比べ業務の区別が曖昧で、ジョブディスクリプション(職務記述書)がない、つまり現場の裁量が大きい日本企業では、やはりそうした取り組みが重要ですね。
髙橋:
はい。やはり日本企業では、よくも悪くもトップダウンで物事は進まないので、大きなビジョンなくして変革遂行は難しいものです。また、現場のチェンジマネジメント的なアプローチも欠かせません。
クラウド化で評価制度も変わる
山本:
チェンジマネジメントと言えば昨今、IT業界では製品・サービスのクラウド化に対応して、ベンダーの評価制度が変わってきたと聞きます。デジタルテクノロジーが進化し、環境が変われば、経営はもちろん人や働き方、評価制度も変化せざるを得ないということでしょう。
髙橋:
クラウドの浸透におけるベンダーの組織文化の変革の動きは、DXにおけるチェンジマネジメントの事例として参考になります。クラウド製品に注力しているある外資系の大手ベンダーは、営業成績にオンプレミス製品の売り上げは含めず、クラウド製品の売り上げのみを対象としたそうです。クラウド製品はサブスクリプション契約となるので、契約タイミングではなく、サービスの利用開始からが売り上げ成績とみなされます。「セールストークが上手いだけの営業」ではバリューが出なくなり、顧客に伴走し続けるスキルが評価されるようになったそうです。
山本:
クラウド製品への切り替えという戦略にあわせて評価制度を刷新し、組織の動きと戦略の整合性を図るという手法ですね。会社の戦略と働き手の評価を連動させ、「どのように人材のスキルを変えていくか」という視点での取り組みが必須なのでしょう。こうした取り組みにより、組織の末端まで戦略を繋げ、戦略の実現に近づいていくのですね。

髙橋:
このような評価制度の変化はクラウド化、サブスクリプションモデルの台頭により、多くのベンダーで起こっています。売り切りではなくサービスを使い続けてもらうことが大切なので、営業パーソンは親身にいい所、悪い所を伝える伴走者となり、さらにベンダーへの信頼度が高まっているように感じます。
山本:
クラウド化に対応するために、トップダウンにより現場の不安や抵抗を乗り超え、マネジメントを変革したケースとして参考になりますね。
現状維持マインドをいかに崩すか
山本:
前述のように、トップダウンによりマネジメントを変革するケースがある一方、僭越ながら日本ではそもそも「何をビジョンで描くべきか」を理解している経営者は稀だと感じています。多くの経営者が語るビジョンとは、あくまでも目先の業績目標でしかなく、業績目標を達成するための指示を主な仕事としています。そして指示を出すだけで後の工程は他人任せといった雑な組織管理に陥っています。
髙橋:
同感です。本来の経営者の役割とは、理屈理論で指示することではありません。ビジネスアーキテクチャを理解し、社内に潜む矛盾やボトルネックをいち早く察知し、解決に向けて先導を切ることですよね。クラウド化への対応はその好例でしょう。
山本:
政治家の方にも見受けられますが、「最後は私が決めます!」という決定権をリーダーシップと誤解しているケースもよく見受けられます。本来のリーダーシップとは、環境変化や混乱が巻き起こる中で「何を論点とするのか」を提示し、社内の議論を喚起し、その調和を図りながら目指す方向を、メンバーを巻き込んで定めていくことではないでしょうか。つまりリーダーシップとは覚悟や精神論だけではなく、組織への深い理解やテクニックが必要となるわけです。この観点で「何もしない経営者」の存在は、変革の障害となり得ると感じます。

髙橋:
日本では社長の任期がだいたい5年ほどです。その短期間にチャレンジして失敗する恐怖で、保守的になっていると感じます。出る杭になるべきではない、という終身雇用制度ならではの風潮も起因しているのかもしれません。欧米では、成果が出なければ次のステップはないので、何もしないことがリスクとされています。自分の代では何もせず、このままで良いだろうという、現状維持のマインドをいかに崩していくのかも課題ですね。
変革人材はジョブ型雇用もあり
山本:
この領域はどうしても文化論とか歴史論、経済論に帰着しがちですが、そうなるとなかなかすぐには動き出せないことが増えてしまいますね。しかし、経営がリーダーシップを発揮していくために、社内への深い理解や変革のためのテクニックの活用をサポートする変革人材をジョブ型で雇用していくという方法であれば、可能だと思います。それによって、リーダーシップの発揮を支えるのです。すぐに雇用形態全体をメンバーシップからジョブ型に変えろという話ではなく、変革人材だけジョブ型にできないかとも考えます。

髙橋:
そうですね。そして私たちコンサルタントのミッションの一つは、今後、経営者候補の人材を育成し、彼らのチャレンジに伴走してともに成功することです。変革の推進力を持った人材、デジタルに精通した次世代の経営者とともに DXを実現し、日本企業の競争力を取り戻すことに貢献したいと考えています。
山本:
最後になりますが、クラウド化といった市場や外部環境の変化により経営やマネジメント、働き方が変化しているように、コンサルティングサービスも変化する必要がありそうです。
髙橋:
例えば、エンジニアの処遇に関して言えば、外部環境の変化により急激に潮目が変わりました。よく知られていると思いますが、15年ほど前のIT業界で、エンジニアの処遇は決して良いものではありませんでした。それから 5年くらいの間にビッグデータというブームが到来し、現在の生成AIのブームにつながる流れの中で、特にデータ人材の処遇は非常に良くなりました。エンジニアの待遇もDXブームの人手不足の中で、大手を中心にかなり改善されています。
市場に火が付けば経営も変わる
山本:
エンジニアのケース以外でも、各企業のDXには、外部環境の変化がかなり影響しています。なによりDXブームにより、ITに疎い経営者もDXに着手せざるを得ない状況になり、企業規模や業種問わず取り組むようになったのだと思います。市場に火が付けば、経営そのものも変化し得ます。経営者は日和見主義な部分もあるので外圧、ムーブメントを作ることで、自ずと経営も変化するのではないでしょうか。
髙橋:
そうですね。次世代を担う変革人材の育成、経営者の代替わりを待つだけでなく、経営を変化させる外部環境を形成していく役割もコンサルタントには求められていくのでしょう。「外圧」もその手段の一つになりそうです。

山本:
202X年の崖が指摘されたり、ERPにも生成AI、AIエージェントが搭載されたり、テクノロジーが加速度的に進化しています。コンサルタントにとっても、常に情報をキャッチアップしスキルを磨かなければならない時代です。逆にやりがいは大きいですね。
髙橋:
本当にそうですね。変化の激しい時代ですから、企業も次から次へと新たな変革を求められます。そこでは、先ほども述べた通り自分たちで変革を乗り切ったという経験が、次の変革にも自信を持って前向きに取り組めるようになります。そんなアジリティ(俊敏性)の高い組織への成長に伴走することは、私たちの大切なミッションです。
エディター・ライター
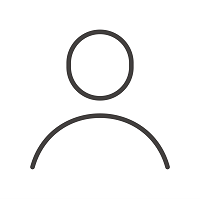
2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)