※議論の成果は2026年に出版予定です。
現場と経営の方向性を合致させる
山本:
経済産業省がDSS(デジタルスキル標準)で定義したとは言え、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の育成は緒に就いたばかりです。処遇やキャリアパスがなければ、育成も進まないでしょう。まず育成に関して、白鳥さんはお客様にどのような価値を提供しているのですか。
白鳥:
私が本部長を務めるConsulting事業本部では、お客様にDX人材育成研修とDX企画立案をセットで伴走支援しています。研修だけだと経験値は身に付きません。LTSのコンサルタントは3か月間、一緒に実際のDX企画を作り上げます。そうすると、LTSが抜けた後も企画が動き続けるのです。
山本:
そのプロセスでビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の役割が理解され、変革活動が推進されれば育成、経験の積み重ねも進むのですね。
白鳥:
はい。あるメーカーのお客様は、経営企画部にビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を確立させるため、各部門の研修とフォローに経営企画部のメンバーを参加させています。ビジネスモデルへの理解を深めるためで、一度受講して終わりではなく、繰り返し繰り返し研修に参加します。また、現場の企画立案にコミットし、実践の場数を踏んでもらいます。実践を積み重ねる点でこうした取り組みは非常に大切です。

山本:
企業のアーキテクチャを把握する人材を経営企画部門から現場の各部門に投入することで、現場に経営の視点が取り入れられることが期待できるわけですね。現場と経営の方向性を合致させ、変革を実現すると。
白鳥:
そうです。また近年は部門横断のコミュニケーション的課題からも、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材のニーズが高まっています。従前の日本企業はメンバーシップ型雇用ならではの特徴として、同期や学閥などによる各部門の管理職同士に強固な繋がりがありました。それによって部門間のコミュニケーションがとれていました。 最近はよくも悪くも人材の流動性が増し、部門横断のコミュニケーション力が弱くなっているのです。
日本独自の方法論が必要
山本:
なるほど。そうした状況もあって、現場への細かい解像度を有しながら部門横断の働きかけも担うビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材が求められているわけですね。しかし欧米発の職能、方法論なので日本独自の企業文化を考慮したビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を考えなくてはなりませんね。
白鳥:
はい。例えば後述する「現場での改善」は日本独自の文化ですね。ジョブ型雇用が主流の欧米で従業員は、ジョブディスクリプション(職務記述書)にない業務はしません。そのため、現場を含めた改善の全工程がビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の管轄となります。一方、日本では現場社員が主導するケースが多いのです。欧米のように現場主導の改善をなくすのではなく、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材と現場で協働して進めるのが適切でしょう。現場の人材が改善を主導しつつ、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の目線も取り入れるという枠組みです。
山本:
欧米ではトップダウンが根付いているので、強権的な変革も可能ですが、日本は現場が一定の力を持っているので、海外と同じ方法論は通用しないですね。日本ではボトムアップ的な機能を担うと。
白鳥:
そうです。日本のビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材は現場に目端が効いて、経営と現場の中間にたって利害調整しながら、企業全体の変革を促すスキルが求められます。

山本:
ボトムアップ型のビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材であれば、やはりトヨタの取り組みが好例ですね。TPS(Toyota Production System)を推進するため、「TPS本部」を設置して部門横断で改善活動の連携を図っていることが有名です。TPS活動を専門にリードする人材を各部門から選任し、各部門から上がる課題や要望をTPS本部に報告することが義務付けられています。TPS本部では報告をもとに、全社状況・経営の意向も考慮したうえで、各部門へフィードバックします。
白鳥:
TPS 本部は、ボトムアップ文化の下でビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材集団としての役割を果たしていますよね。現場主導での改善を機能させながら、経営の視点も取り入れていく点で「日本流」の象徴だと思います。
キャリアを確立するために
白鳥:
ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を育成し経験を積んでもらったとして、キャリアパスが課題となります。専らプレイヤーと認識されることが多く、管理職としてのキャリアパスが確立していないのです。
山本:
ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材は、ビジネス設計を担う社内コンサルタントとしてだけでなく、政治力をもって新たな仕組みを訴求する管理職としての役割も担います。経営がマネジメント、キャリア設計までできたらよいのですが、現段階ではそこまで手が回らないでしょう。
白鳥:
そう考えると、企業内でビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を育成し、配置することは多くの企業にとって難しいことかもしれません。ですからジョブ型での育成、雇用も一つの手です。また、会社の外に「大きなビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材コミュニティ」をつくり、活動範囲をひとつの企業に留めることなく、人材市場で流動していく方が活躍できるのかもしれません。
山本:
企業内でどう処遇するかという議論に限定せず、市場でシェアするというイメージですね。
白鳥:
はい。DXプロジェクトでは、課題が特定できないまま短期的な業績目標を無理矢理に設定して、失敗する例がまま起こります。DXが目的化し手段と逆転してしまうのです。ジョブ型で配置できれば、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の客観的・長期的な視点がDXにも良い影響を及ぼすでしょう。

山本:
そうですね。変革への合意を得る段階でも、活躍が期待できますね。合意を取るためのコミュニケーションが上手くいかず、第一歩を踏み出すことができないケースも多々あります。そこでビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の「ファシリテーションスキル」が活きてきそうです。
白鳥:
DXの取り組みは、事実を明らかにし論点を棚卸しして課題を提示、課題解決策とそのメリット、デメリットを提示してステークホルダー間の合意を得るという段階的なアプローチが必要です。ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材により、滞っているビジネス変革が進むことが期待されます。
山本:
経産省のDSSに関しては、改訂するためのタスクフォース(TF)が始動しており、私が主査を務めます。「ビジネスアーキテクト」をさらに「ビジネスアーキテクト」「ビジネスアナリスト」「プロダクトマネージャー」の三つの役割の構成に変更する方向で、今後検討される見通しです。より解像度を高く、具体的なイメージをつかみやすいようにしたいと考えています。

白鳥:
期待しています。ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の育成が肝要なのは言うまでもありません。そしてビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材が将来、企業変革をリードしていけるよう、その成長とポジション、キャリア、コミュニティや人材市場を確立させるのがLTSの役割だと自負しています。時間の経過を待つだけでなく、未来の経営が変わるような社会構造を形成していきたいですね。
山本:
LTSがこれまで撒いてきた種を咲かせ、日本の企業変革の一助になりたいですね。白鳥さんの活躍も楽しみにしています。
エディター・ライター
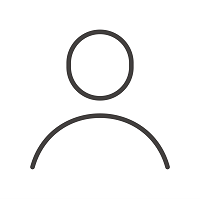
2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)











