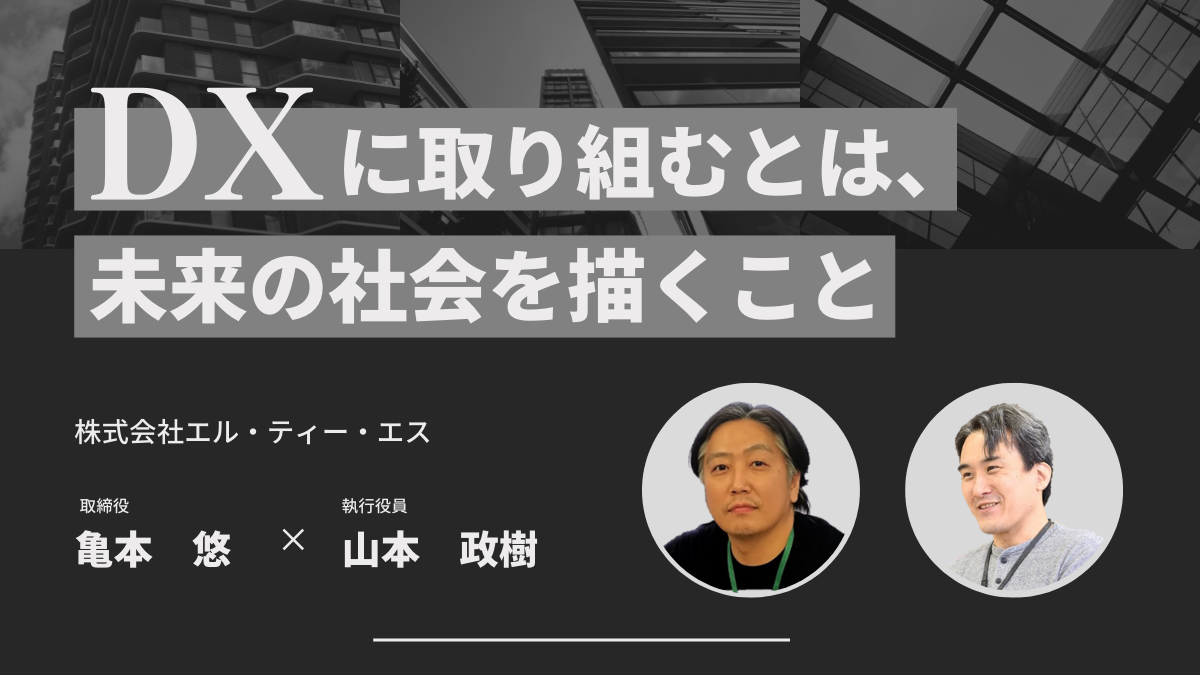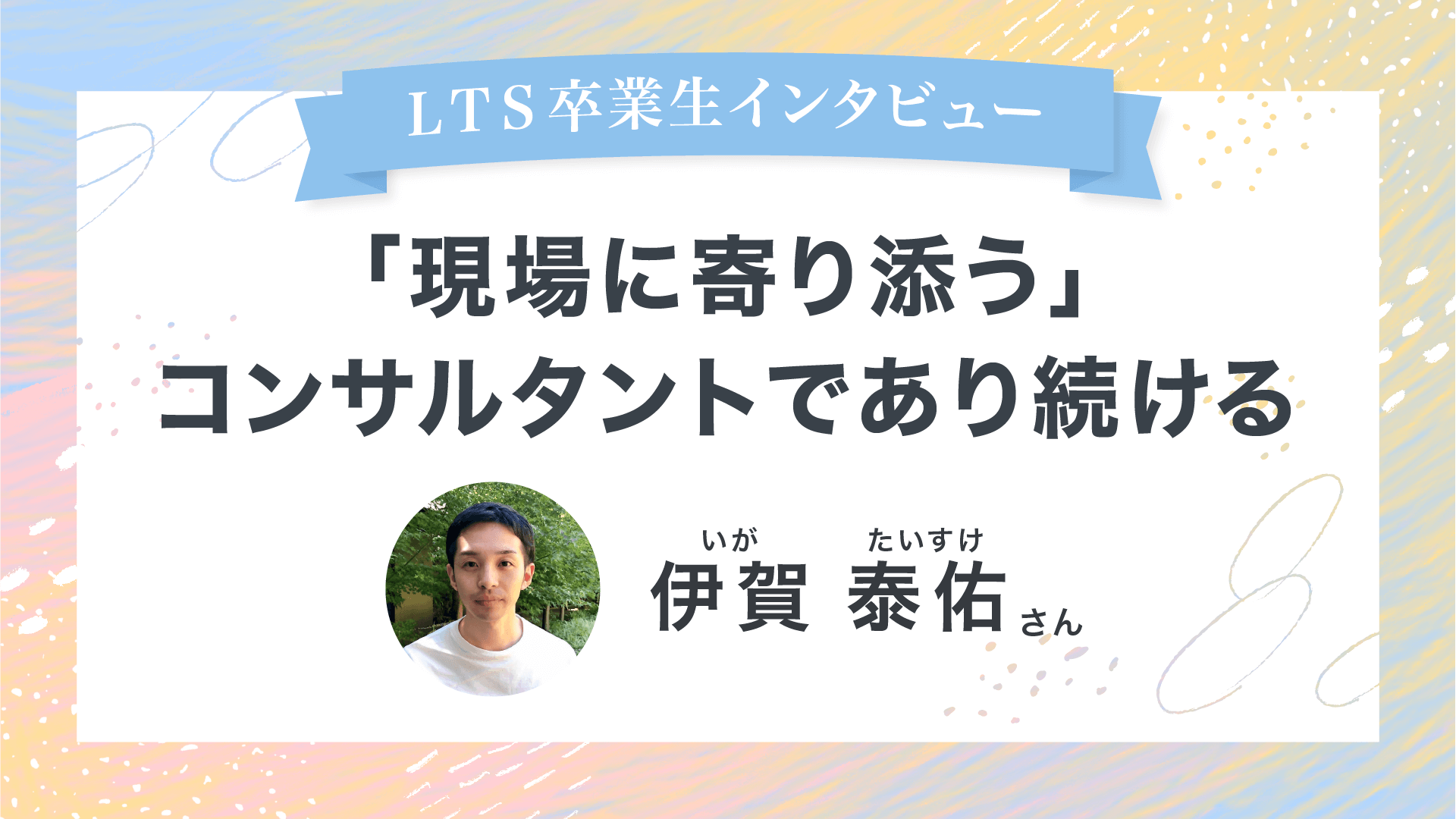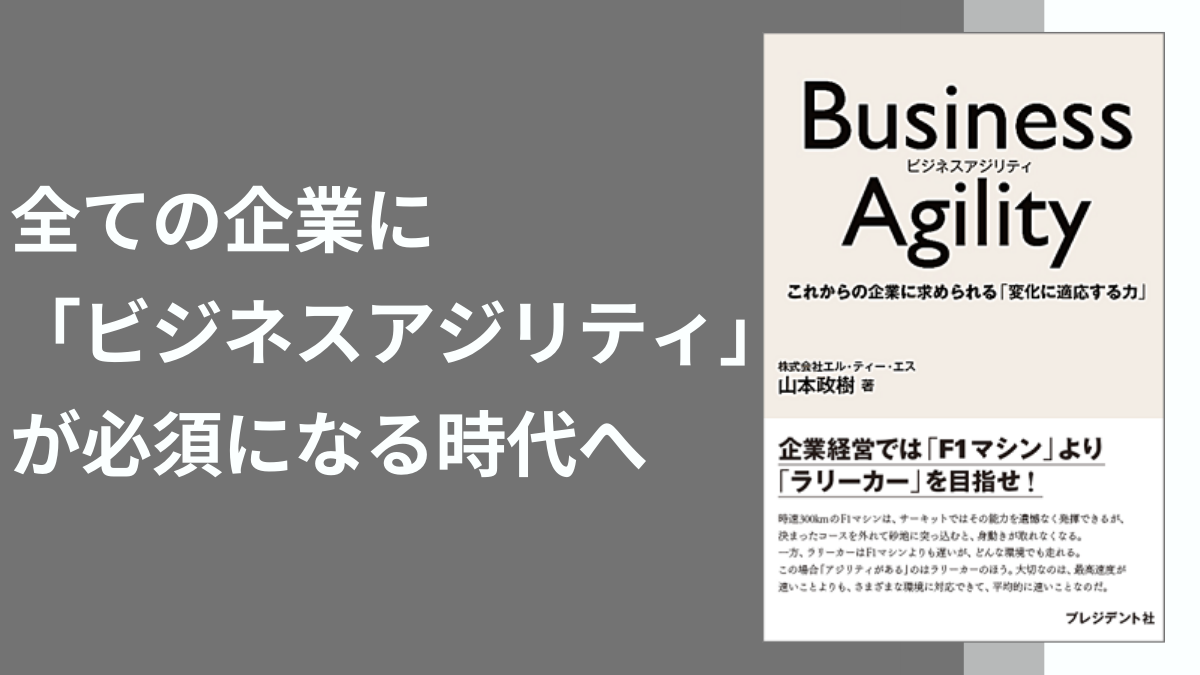少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、地方自治体は業務効率化と住民サービスの維持・高度化をどう図かっていけばよいのでしょうか。一つの解がDXです。LTSは鹿児島市の「DX推進サポーター事業」で2025年9月までの3年間、コンサルタント2人を派遣し自治体情報システムの標準化・共通化、グループウェア刷新といったプロジェクトを推進しました。「地方自治体でDXを進めるために必要なことは」―。鹿児島市の下鶴隆央市長と、LTS取締役副社長執行役員の亀本悠が対談しました。

ラ・サール中・高、東京大学法学部卒。IT系コンサルティング会社勤務の後、2011年から鹿児島県議会議員を3期務め、2020年に鹿児島市長初当選、現在2期目。趣味は将棋(高校生活3年連続で、高校竜王戦で鹿児島県大会優勝)、クイズ(第4回KTS鹿児島クイズ王で優勝)。サッカーの鹿児島ユナイテッドFC、バスケットボールの鹿児島レブナイズの大ファン。(2025年9月現在)
プレスリリース LTSの鹿児島市「DX推進サポーター事業」が完了しました コンサルタント2人を3年間派遣。自治体情報システム標準化、産学官金連携など支援
「死ぬ気で頑張る」では組織は持たない
亀本:
LTSからコンサルタントを派遣させていただき3年間、鹿児島市DX推進サポーター事業が2025年9月で完了しました。成果はいかがでしょうか。
下鶴:
この 3年間で大きな変化がありました。まず、紙を使うことに罪悪感を覚える感覚が庁内に広がりました。また、グループウェア(M365)を導入したことで、コミュニケーションコストが劇的に下がりました。出張先や出先でも大量の紙資料を使っていた私の打ち合わせも、オンラインで済むようになりました。
亀本:
下鶴さんが市長に就いたのは2020年12月です。約2年後からDX推進サポーター事業に取り組みました。理由はやはりDXの遅れを感じたからですか。

下鶴:
1期目のマニフェストに掲げた民間人材の積極的登用の一環としてDX推進サポーターを募集しました。正直に言ってDXは遅れています。まずは「遅れていることを認識する」ことからでした。業務に大量の紙を使っていましたし、繁忙期の窓口は大混雑して「こんな市役所に税金払いたくない」と苦情が来るほどでした。
しかし庁内にDXを推進するノウハウはありません。ゼロからの立ち上げは時間がかかりますから民間活力を利用しようと。当初の課題は、職員のデジタルへの“見方”を変えることでした。
亀本:
私も鹿児島で過ごしたことがありますが、鹿児島市役所の窓口は東京ディズニーランドより並んでいると言われていたそうですね。
下鶴:
はい。職員と懇談を重ね、目指す姿を「自走するDX」としました。外部の方に入ってもらったDXで一時的には効果は出たとしても、自走しなければ意味がありません。まずは、職員にデジタルは良いものだと感じてもらうような取り組みが必要と考えたのです。

亀本:
自治体は公平性が求められますし、ソリューション導入には多額の予算が必要です。自治体は重要な社会インフラですが、私の経験上、インフラ企業は業務を止めてはならずミスも許されないため保守的になりがちで、変革は特に困難ですね。
下鶴:
はい。さらにソリューションやシステムの導入には億単位の予算がかかります。予算は単年度主義で議会説明と理解が欠かせません。また、職員は皆、真面目なので「最後は自分たちが死ぬ気で頑張れば良いいい」という文化なのです。 ですから、自治体でDXを進めるには、誰かが旗を振らなければなりません。
亀本:
人件費も定量化すれば簡単に億は超えていますね。
下鶴:
そうです。定量化することは本当に大切です。死ぬ気で頑張るだけ、からきちんと業務の効率化・高度化のためDXの旗振りをする必要があります。まして人口減、生産年齢人口が減少するこの先は「頑張れば良い」では組織は持ちません。これを象徴したのが新型コロナウイルス禍でした。
パンク寸前のコロナ禍がきっかけ
亀本:
コロナ禍は2023年5月にWHO(世界保健機関)が緊急事態宣言を終了し、国内でも2類相当から5類感染症になりました。LTSがコンサルタント2人を派遣したのは2022年9月ですから、コロナ禍真っ只中でしたね。
下鶴:
鹿児島は中核市ですから保健所を持っています。コロナ禍当初、感染者が1日当たり数十人の時は、陽性の人に電話連絡して…という対応が可能でした。それが、100人を超えてくると全部局から職員を動員して徹夜で対応するようになりました。300~400になるともう回らなくなり、陽性の告知が 2、 3日遅れるようになりました。
感染者がこれ以上増えたら、もう市役所の業務全体がパンクしてしまう状況でした。そこで「連絡はショートメッセージ(SMS)にしましょう」と指示しました。こうした際、よくあるのが「スマホを使えない高齢者たちをどうするのだ」という批判です。しかし、違うのです。SMSで 9割の電話連絡を削減し、残りのリソースを高齢者対応に回すということです。デジタル化はむしろ高齢者に対応するためです。ピーク時、感染者数が2000人を超えた時も、なんとか対応することができるようになりました。

亀本:
デジタル化の意義を言語化することは非常に大事ですよね。そのケースで言うとSMSを使うと届かない人がいるから、SMS利用はやめようという結論 になりがちです。でも、なぜ電話にこだわるのですか、と。限られた職員のリソースを最大化するためにデジタルを使うわけですから。
下鶴:
やはり行政には公平性と正確・確実さが求められますから、変革への不安も理解できます。また、民間であれば、DXで業績が上がれば給料もボーナスも増えるでしょう。しかし、役所の給与体系はそうではないので、チャレンジへのインセンティブを持ちにくいこともあります。私は市長に就いてから「とにかくチャレンジしよう」と伝えています。
亀本:
コロナ禍のような非常事態が起きたことで有事の際、組織内に変革する文化がなく、変革人材もいないということに民間を含め皆、気づいたと感じています。あるインフラ企業もコロナ禍を機に変革の必要性を痛感され、LTSが伴走させていただきました。自治体も特性上、変革とは遠かったかもしれませんが、コロナ禍を機に変わったのですね。
人口減と高齢化にどう対応するか
下鶴:
はい。変革の必要性は、コロナ禍対応だけではありません。鹿児島市を含め多くの地方自治体は日常的に人が足りていません。鹿児島市が地元で人気の就職先であることは間違いありませんが、職員の採用倍率はこの5年間で急激に落ちています。技術系は1倍を確保するのが精いっぱいで、事務系もかつては10倍だったのが3倍程度です。理由はシンプルで、労働力人口が減少しているからです。
亀本:
バブル期後半に就職した世代が現在 60歳前後ですよね。当時は官民とも採用も多かったので、あと数年でその世代が一気に職場を去ることになります。従業員5000人ほどのある会社は、2020年代後半には定年で1500人ほどが退職するそうです。ですからDX、業務ナレッジの標準化に追われています。
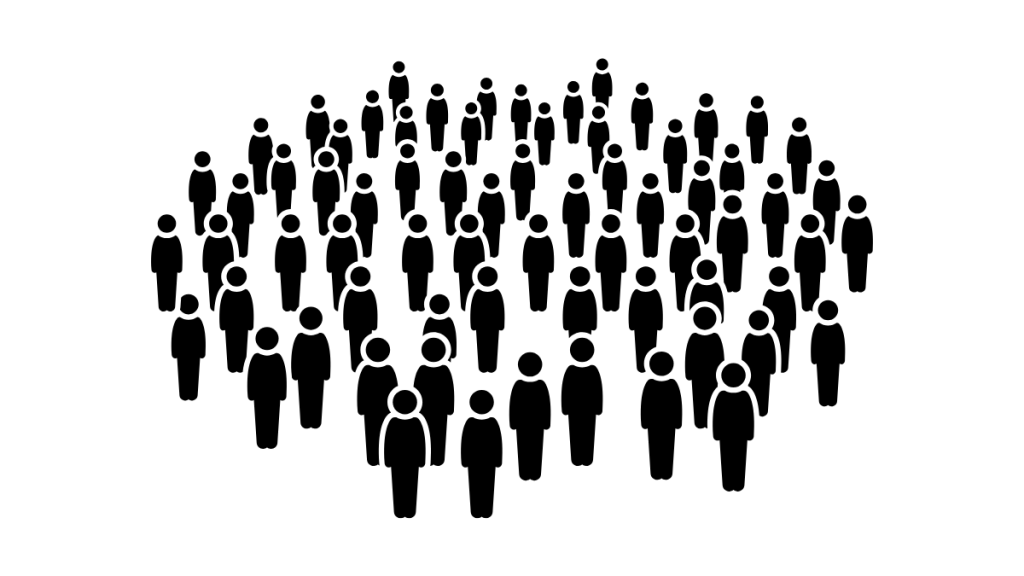
下鶴:
鹿児島市はそこまでドラスティックではありませんが、似た状況です。なにより市町村は福祉の担い手であることが最大の課題です。団塊世代が後期高齢者となりこの先10年、福祉需要は一気に増します。ここはどう対応するか、強烈な問題意識があります。DXで仕組み変え、リソースを確保しないと持たないでしょう。
亀本:
人口減と高齢化は日本全体の課題ですね。加えて構造的な課題として、企業でもITやデジタル、テクノロジーの専門性を持っている人財は少なくユーティティプレイヤー、ジェネラリストが多い点があります。多くの企業でITといった専門領域は外部ベンダーに丸投げされてきました。DXはもちろん、ビジネス自体がデジタル上で動くようになり、気が付くと日常業務も企業変革もできる社内人材が見当たらないと。ですから現在、いまリスキリングが言われたり、M&AでIT機能を持った会社を取り込んだりという動きがあります。
下鶴:
民間と変わらず、自治体も働き方を含め変革しなければなりません。デジタルに強い人材は多くなく、今後はそうしたスキルを持つ人材を採用しないとなりません。また20年、30年先の将来を支える 30代 40代のリスリスキリングが必要です。現段階ではまず、その領域のリーダーになるような人を育てる必要があります。
DXの第一段階に手ごたえ
亀本:
市役所の外に目を向けると、地方の中小企業もやはり人手不足ですし、単独でのIT投資は難しいと思います。大手や中央と競争力の差が開く一方です。地元企業に、そうしたサービスやプラットフォームを提供するというのはいかがですか。
下鶴:
その前段階ですが、個人的な問題意識として、中小企業や経営の方々に現在どういうテクノロジーがあって何ができるか、経営や事業に応用できないか、そんな勘所をつかんでもらう場を作れないかなと思っています。DXに関心のない経営者はいませんから。

亀本:
福祉需要への対応も課題とのことですが、最も重要な市民サービスへの展開はいかがですか。
下鶴:
もちろん市民向け、身近なサービスを便利にして行くことが必須です。乳幼児保育や子育中の市民へのチャットボット、公民館の予約システムと、高齢者デジタル相談会など世間から見ると簡単な話かもしれませんが、こうしたサービスをさらに充実させていきます。さらに、マイナンバーカードの取得率を上げる必要もあります。
亀本:
LTSとしても、地方自治体のDXに伴走できたことは非常によい経験、ナレッジとなりました。この先、市長や市政の課題、問題に対してどんなサービスを提供し、どんな活動ができるか、現場と継続的に進めます。ありがとうございました。
下鶴:
今回の事業で、DXの第一段階「デジタルで便利になる」意識を広げ、職員の働き方も改革しつつあるとの手ごたえがあります。第二段階はマイナンバーなどさまざまなデータに基づき市民一人ひとりに最適化した政策を進めていけることを目指しています。LTSには今回、そのための最初の一歩を力強く進めさせてもらったと感じています。