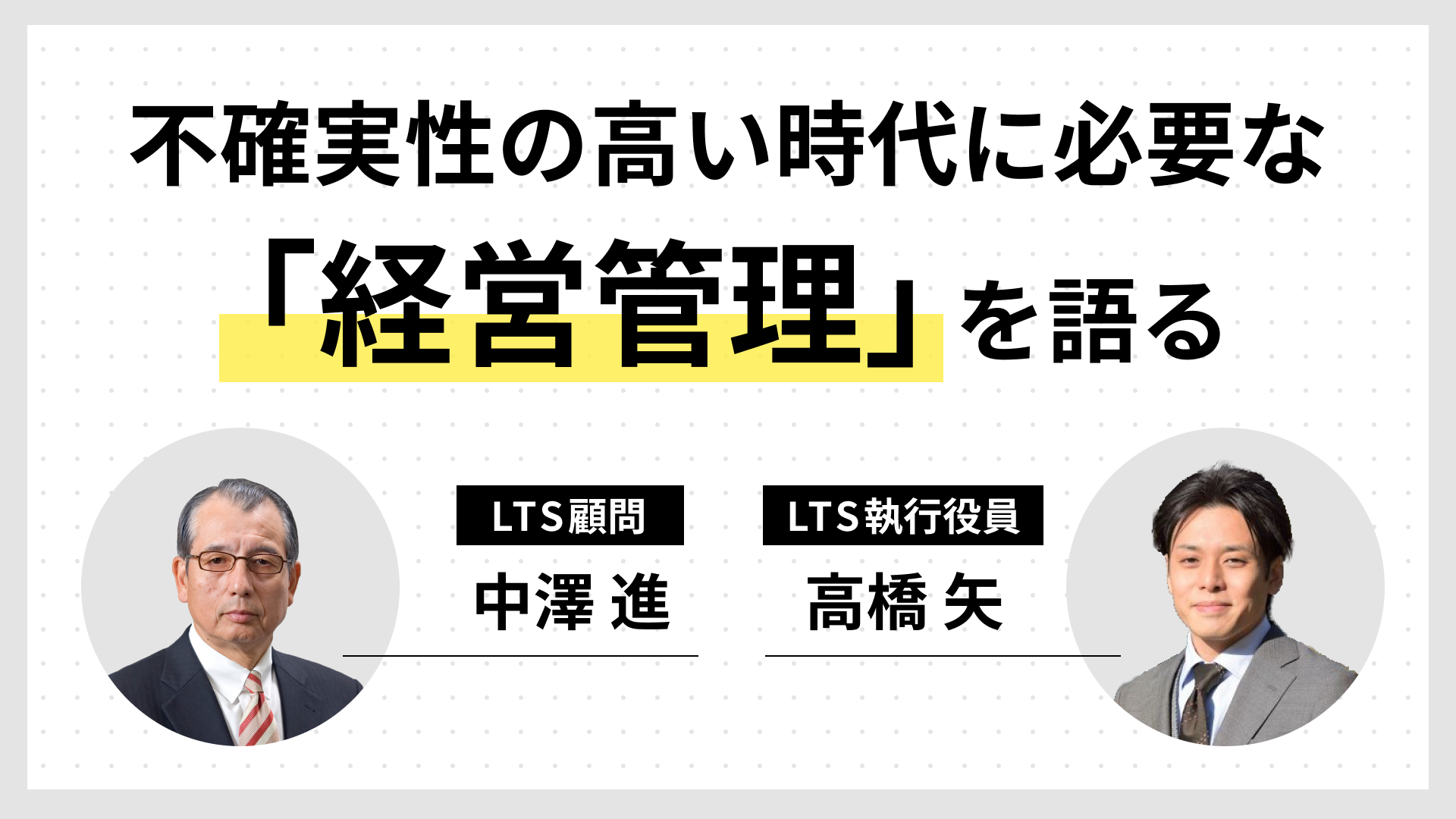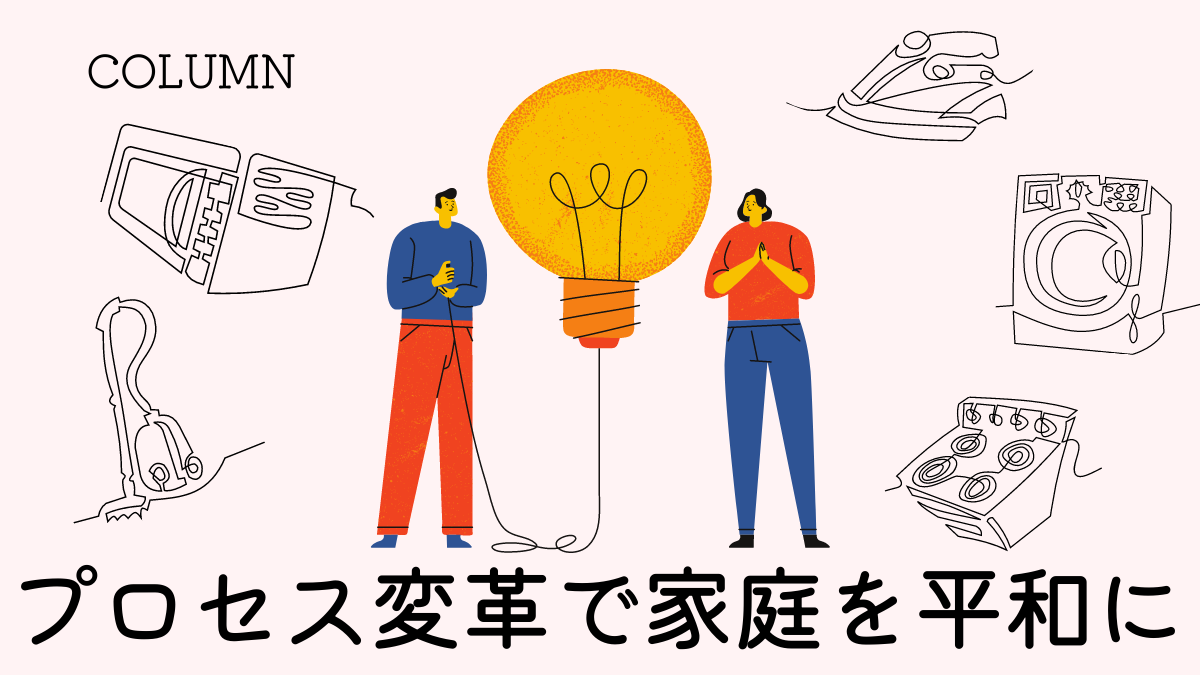1971年日本IBM入社。経理・財務部門の業務改革、管理会計、内部統制分野でのコンサルティング及び会計システムPJの実績多数。2002年IBM取締役に就任、2007年中澤会計情報システム研究所を設立。同年ビジネスブレイン太田昭和会計システム研究所所長に就任。2016年よりエル・ティー・エスに参画。日本CFO協会主任研究委員。(2021年9月時点)
「将来事実」でアジリティのある経営を実現する
髙橋:
ここでは、「アジリティのある経営管理」に必要な要素を議論したいと思います。これまでの会話の通り、柔軟性・軌道修正力を保ちながら迅速に意思決定をしていくことが、今後より一層求められていきますよね。
中澤:
そうですね。従来のモニタリングフィードバック、いわゆる予実管理。予算と実績を対比して次のアクションを検討する手法は、今の時代において時間的に間に合いません。勝負に負けてしまいます。私が着目するのは「将来事実」です。これは単なる見通しとは異なり、より精度の高いデータです。将来事実でビジネスの先読みを行い、先手先手で分析し、活動計画を立て、行動していくという考えです。年度が始まった瞬間は、年度予算が年度末というタイミングの将来事実です。年初から3か月経つと、ビジネス環境は変化するので、年度末である9か月先の将来事実も変化します。その事実を基に、BS/PLを作成します。そこで、9か月先の年度末における経営状況が見えてきます。もし、あまり芳しくない状況であれば、その時点で9か月間の活動計画を作成し、即座に行動に移します。これからは、このような予算管理サイクルが求められます。
髙橋:
まさしく軌道修正をしながら、経営の目標達成に導くアプローチですね。DDP(Discovery Driven Planning:仮説指向計画法)という経営管理手法についてお話をした通り、企業活動は過去に立案された計画に基づいて遂行されています。計画を遂行する際には、ビジネス環境の変化に対して、当初計画とのズレをどれだけ早く認識できるかが肝になります。DDPでは計画の根拠となった仮説や前提のズレを認識することで、早期の軌道修正を実現します。計画の中身は仮説・前提の集合体なので、過去の意思決定の根拠情報がしっかりと可視化され管理されていれば、外れた仮説のみを新たな仮説に置き換えることで、軌道修正をかけることが可能となります。現状では、仮説・前提といった定性的なものを含む情報を、しっかりと管理できている企業は少ないです。
仮説・前提のモニタリングで、軌道修正要否を早期に把握し乖離幅を測り、将来事実を再作成することで先読み精度が高まります。その結果、「アジリティのある経営管理」に近づけるのではないでしょうか。経営会議などでも「先月の予算に対して実績はどうだったか」という、予実分析で回しているところが多いようです。着地見通しを作っていく、という動きもあります。しかし、その情報の精度がまだ高くありません。中澤さんのおっしゃる「将来事実」というほどの精度ではありません。営業の引き合い情報など、特にトップラインには将来事実を補足しやすいので、そのような情報を営業からうまく吸い上げられる仕組みができないかと考えています。
中澤:
そうですね、予算は元々仮説ですので、年度末時点の仮説と言い換えることができます。毎週・毎月年度末の仮説を見直しましょう、でもいいと思います。
髙橋:
特に、変化が激しい業界においては、そのくらいの頻度で仮説の見直しが必要になるのでしょうね。しかし、今現在の業務ですら、毎月のデータ収集、分析、レポートの業務でひっ迫しているのに、追加の業務が発生すると業務が回らなくなりますよね。そのため、“今の時代に必要な経営管理業務”を支える仕組み(システム)の重要性が高まってきそうです。
中澤:
将来事実を元にした仮説作成は、スピード感が求められます。売上、受注、稼働率など、複雑な計算をしなくとも把握出来る数値を使用します。このような数値は予算と呼ばず、目標やターゲットと言ったほうが良いでしょう。成果指標であり、活動指標です。このような数値を基に1か月、1週間単位で、ターゲットを見直す、という仕組みが良いのではないでしょうか。その仕組みは、予算編成を行う仕組みと同じシステムです。日本の企業で「予算」というと重く感じますが、ターゲットと言えば軽い感じがあるでしょう。このような数値であれば、1週間くらいで組織全体で積み上げられるでしょう。この延長線上に、ローリング予算※1があります。ローリング予算を機能させるためにも、長くとも1週間くらいで予算設定ができる数字でないといけません。
中澤:
この仕組みには、通常の予算編成を行う時のワークフローシステムが活用できます。年度の予算編成のためだけのシステムであれば、投資効果がどうかという議論になります。しかし、毎週・毎月使うため、十分に意味のある投資になるのではないでしょうか。これからのモニタリングフィードバックは、予算実績という話ではなくなります。将来事実を見通して仮説を作りつつ、活動の先読みしていくプロセスとして、モニタリングフィードフォワード※2と言った方が良いかもしれません。そういう感覚を持ち、新たな仕組みを作っていきましょう。
髙橋:
おっしゃる通り、これからはフィードフォワード型の経営管理が必須です。その実現に必要な情報の定義、定義した情報をどのように収集・加工・レポートするのかという業務プロセス設計、それらを効率よく迅速に回すための経営管理システムが求められるのだと思います。
時代背景に合わせた経営管理制度の改革を
髙橋:
ここまで、様々な問題意識やそもそも経営管理って、というところをお話ししてきました。ここからは、時代や意見を踏まえ、求められる経営管理を議論したいと思います。環境変化と意思決定スピードに対応する、アジリティを持った経営管理の仕組みやシステムの構築。単純にITを導入して経営管理業務の効率化を図るだけでは、これまでと変わりません。もっと本質的なところにアプローチしていかないと、今後求められる経営管理に到達できないのではないかなと思います。
中澤:
基本的には、組織としての先読みの力が重要です。このVUCA時代、経営管理においては先読みの力は必須だと考えています。今回の新型コロナもそうですが、自然災害は突然に起こります。先読みし、将来事実を把握しておけば、環境変化に対応する時間的な余裕が持てるようになります。これまでの実績を分析し経営判断するのではなく、常に半年後・1年後の数字(将来事実)をベースに経営を動かしておくと、その先の対処もやりやすくなります。そのような仕組みを持つことは必須ですね。
髙橋:
そうですね。昨今の時代背景に合わせて、抜本的な経営管理制度改革を中心とした、企業変革が求められます。組織としての先読みの力は「実績検証型から仮説検証型へのシフト」です。勘と経験の要素の最小化や属人性の最小化(=多様性への対応)は「データドリブン」で対応できます。先読みに対し、「なぜそう考えたのか」という仮説の根拠を明確にしていくところが、先読みしたものをコントロールする要素の一つになると思います。
中澤:
それを、日ごろの年度の管理会計の中でも、取り入れていくのが良いでしょう。あとは、人に依存するようなメカニズムを最小化することが大事です。誰それの読みが当たったとか、誰それに聞こう、では良くありません。データ収集や分析のプロセスを定義して、そこへ自動的にデータを流し込み、最終的にはトップマネージメントが判断するという仕組みが望ましいです。経営者の判断は経営者の意思によるアナログ判断ですね。アルゴリズムに任されるようなものではないと思います。大量のビジネスデータが整理され活用しやすい、見やすい状態で存在すれば、経営者判断がよりスピーディーで、より高度なものになるでしょう。デジタルテクノロジーが大いに活躍できる領域ですね。
髙橋:
はい。予算管理にしても、当初立てた計画に固執して、何としてもそれを必達せよ!という状態もあるかもしれませんが、それは経営管理ではありません。1~2か月経つと環境は新しくなるので、都度ターゲットを変えていかなければなりません。これは、組織の構成員の士気を高めるためにも必要です。
中澤:
年初に立てる予算は、それなりのものを作らなければいけません。特に、上場企業のトップマネージメントにとっては、この数字が市場に対するコミットメントになり、投資家との会話のベースになります。ただし、高橋さんが言われるようにビジネスはスタート直後から、毎月何かと変化していきます。その中で、ボトムライン(利益)を確保するのが経営者の責務です。そのような環境下で、年初に立てた予算という仮説に拘泥していると、機動力を発揮できません。結果として、ボトムラインを確保できなくなります。
そこで、新たなターゲットという仮説を臨機応変に設定し、経営資源の再配置を行い、ボトムラインを確保すべくビジネスを遂行する。そのような機動性がこれからの時代は必須です。会計年度に拘らないローリング予算や、フォーキャスティング※3に基づく、フィードフォーワード的モニタリングなどが、有効なツールとなります。中期経営計画においても、機動性の確保という点から、DDPの持つ中計の仮説の可視化と、仮説のリスクマネジメントの考え方は有効なツールとなります。
髙橋:
それに併せて、モラルのメンテナンスという点にも注目していただきたいです。結局、人の士気をどのように保ち、目標達成に向かうかが大切です。経営管理という枠組みの中では、この意識を持たせる管理ができていないことが往々にしてあります。結果として、コントロールが効いてない状態と同じになっています。また、そのような管理体系で、現場がモチベーションを高く保ち動くための、業績評価の考え方も変えていく必要があります。常に公平感・安心感がありながらも、状況変化に合わせた適度なストレッチとチャレンジを促す仕組みが理想です。さらに、組織構成員自らが自律的に判断できる人材育成と仕組みの構築も必要です。日本企業が取り組んでいた自律的なカイゼン活動は一つのヒントであり、ビヨンドバジェッティング※4の考え方が参考になります。
経営管理の仕組みから見るDXの本質
髙橋:
少し前まで、DXの本質は?という議論をよく耳にしました。その中では単純に業務をデジタル化することだけではなく、「デジタル技術を活用して、人や組織が継続的に変化をする変革力」こそがDXの本質である、という見方が徐々に強くなっています。変化が激しい時代、一過性の取り組みではなく常に変化に対応できる変革力が必要となるという意見は納得します。経営管理領域におけるDXも同じですよね。集計・分析・レポート業務のIT化も大事ですが、変化に対応するケイパビリティというところまで見据えて問題を捉えることが必要だと考えています。
中澤:
基幹系業務へのERPシステムの導入、請求書のEDI化、経費精算システム等の普及により経営管理に必要なデータの取得が容易になりました。経営層のITリテラシーが高まれば、必要に応じて経営に必要なデータを自らアクセスし、分析できるようになりますね。そうなると、データを集めるとか整理するとか分析するとかいったスタッフワークが不要になってきます。また、各種取引データの会計的精度が上がると完全自動仕訳化が実現し、ブッキングに関わる経理部門の仕事は不要となります。そうなると、管理部門の役割や求められる能力が大いに変わってきます。そこまで考えてデジタル化に向き合うのがDXです。
髙橋:
DXはITシステムのみならず、企業文化(固定観念)を変革することが重要とも言われているかと思います。それこそ、これまでの過去実績中心の経営管理という固定観念を壊して、将来事実中心の経営管理のための情報収集、分析の役割を、経理・財務部門が担っていくということも考えられます。固定観念に捕らわれず、あるべき業務を追及する文化づくりをする。そして、新たな業務に対してデジタル技術を活用して業務最適化を実現していく。こうしてバックオフィスとしての新たな価値を創出し、その価値に現場がより素早く変革し続けることを支え、ひいては会社全体のDXに繋がっていけばよいなと思っています。
また、経理部門のブッキングに関わる仕事をなくしていくには、業務プロセスの整備や標準化といった取り組みが大事になりそうですね。
中澤:
業務プロセスの整備は、データドリブン経営の基盤構築の大前提ですね。先で話題にした、適切な勘定科目を持った会計情報は、特に重要なデータ基盤になると思います。そのようなデータ基盤が整備されると、経営管理部門の仕事の質は変わってきます。その意識改革が重要です。データ収集・分析・レポート作成は全てデジタル化されますので、空いたワークロードで現場のみならず、経営層のITや会計に関するリテラシーを向上させるなどの啓蒙活動を担うことも、重要な役割になってくるのではないでしょうか。
企業カルチャーに合わせた管理会計の仕組み作りへ
髙橋:
中澤さんも著書の中で語られていましたが、管理会計の役割は、“経営者の意思である戦略を(会計)数値を使って実行に移し、企業の持つ限られた経営資源を選択した領域に集中させる事である”。また、“企業の各組織管理層の構成員が、経営の意思に沿ったアクションを取れるような数値を提供していくと共にその結果をタイムリーに把握する仕組みともいえる“と。これは、まさしく「数字を活用して人・組織が動きだす経営管理」という、LTSが大切にしている戦略の実行を支えるという機能も果たしていると理解しています。私自身ここが重要だと考えており、これを大事にできるような経営管理のサービスを生み出せればと思っています。
中澤:
この対談の中で、LTSの事例も出していただきましたよね。そのような、自社でどうやっているかというのが、お客様には参考になると思います。また、LTSでできていない箇所についてはその原因を説明することで、お客様の中での阻害要因を解消する手助けにもなるのではないでしょうか。
髙橋:
はい、おっしゃる通りだと思います。LTS社内で見ても、「数字を活用して人・組織が動き出す経営管理」が実現できているとはいえません。数値をどのように作成しレポートするか、といった数値作成のプロセスと仕組み化だけでは実現はできません。これまでの議論のまとめのような形にもなりますが、経営管理とは、トップ・ミドル・ボトムを繋ぐための、コミュニケーションツールであるとも言えます。
コミュニケーションの品質やスピードを上げるために、
・全社員が信頼できるデータの提供
・信頼されるデータ生成のためには経営管理には関係ないとも思われるが、営業・購買・製造も含めた業務のルール整備と統制機能強化
・データに対する定義と管理強化
・その情報を必要な人にタイムリーかつ扱いやすい形で提供する仕組み
・データを活用して現場を動かすための現場の士気コントロール
・現場の士気向上ための、上司・部下との予算時点コミュニケーションの変革
・人事制度(目標・評価・報酬)をからめた、モチベーション管理
など、業務プロセス整備・統制、データマネジメント、人事領域までを含めた様々な取り組みが必要になると思います。そして、それぞれが別々の分断したテーマで改革を進めるのではなく、「数字を活用して人・組織が動き出す仕組み作り」というテーマに沿った、全社的な取り組みとして挑戦をしていく必要がありますよ。まずは、LTSの中で実現していきたいです。これらは、アジリティや経営管理DXにもつながるものだと考えています。
中澤:
そうですね、そこには成熟度やカルチャーなども関連しますので、その企業にあわせた提案が出来るようになると良いですね。予算管理のフレームワーク自体は、各企業や業態毎であまり変わらないと思います。その運用の仕方や、KPIをどう設定するかなどは各企業の色が出ますので、そのあたりをお客様と議論できたら、楽しい仕事ができそうですね。
髙橋:
本当はこういう取り組みをしたいと考えているミドルマネージメントが、目の前の業務に忙殺され時間すら捻出できない状況も多いのだろうと思います。経営管理のロードマップを描いていくうえでは、そのような想いのある方たちの時間を作るために、足元の業務の効率化・デジタル化を進めていくことが一歩目になるのではないかと考えています。昨今は、予算編成・分析・シミュレーションまでを安価に支援する、経営管理ソリューションが増えています。導入期間も3~6か月という事例もあります。まずは、今現在時間を取られている業務を、ソリューションの力を借りて軽減し、高度化に向けた取り組みに移るのがよいと考えています。
中澤:
欧米企業では、経営者がトップ主導で経営の舵取りのみならず、業務改革までもリードするのが当り前の世界です。スピード感はありますが、社員の納得感はある程度無視してでもやり抜くという感じです。多くの場合、人員の再配置などが伴うなど、厳しいものがあります。それに対し、日本の企業文化では、まだまだミドルマネージメントがリードする、ミドルアップミドルダウンが主体です。スピード感には欠けるきらいがありますが、全社合意の下、運用段階では極めて力を発揮するといって良いでしょう。スピード感ではトップダウン、合意形成ではミドルアップミドルダウンということです。VUCA時代、トップダウンの傾向を強くしなければいけないことは事実ですが、この辺りの強弱の付け方は各企業の持つ文化・歴史に依存します。我々は、そのような個々の企業の状況を熟知した上で、お客様の立場に立って経営者の方々、現場の方々に、デジタルテクノロジーの効果的な活用方法も含めて、適切なアドバイスが出来るようになりたいものですね。
ライター

社内システム開発PJに携わりながら、ビジネスアナリシスやアジャイル開発スクラムを勉強中。Scrum Alliance認定スクラムマスター(CSM)、アドバンスド認定スクラムマスター(A-CSM)、Outsystems Delivery Specialist、IIBA ECBA、IIBA AAC保有。(2025年6月時点)