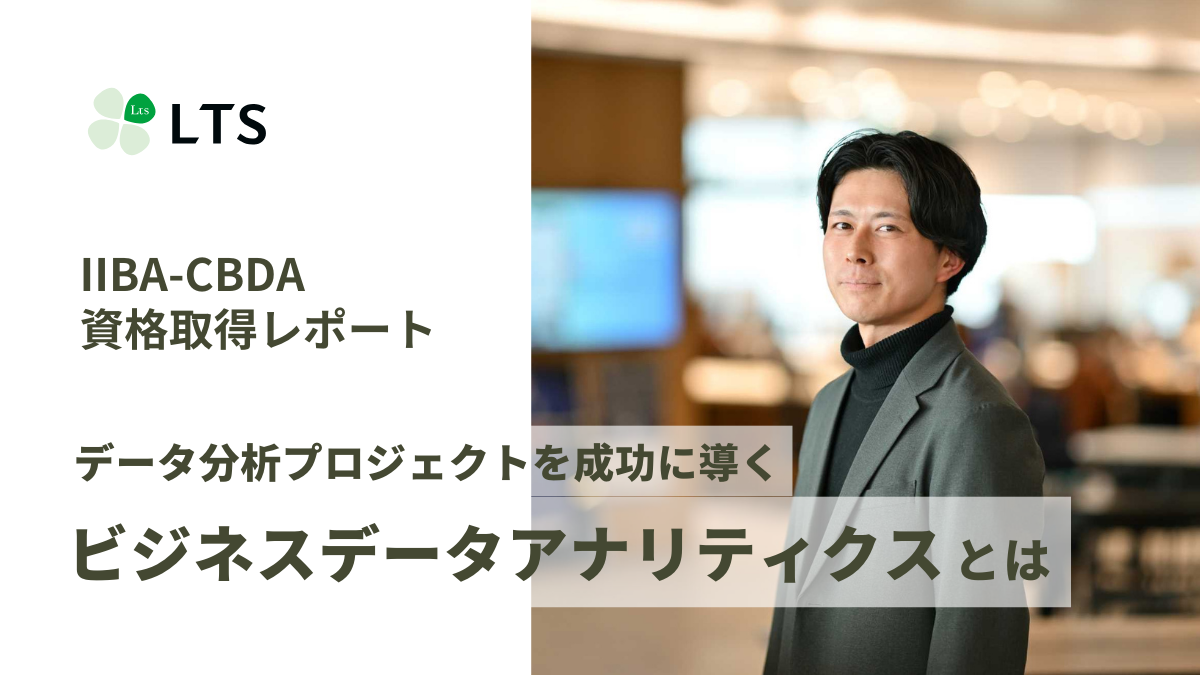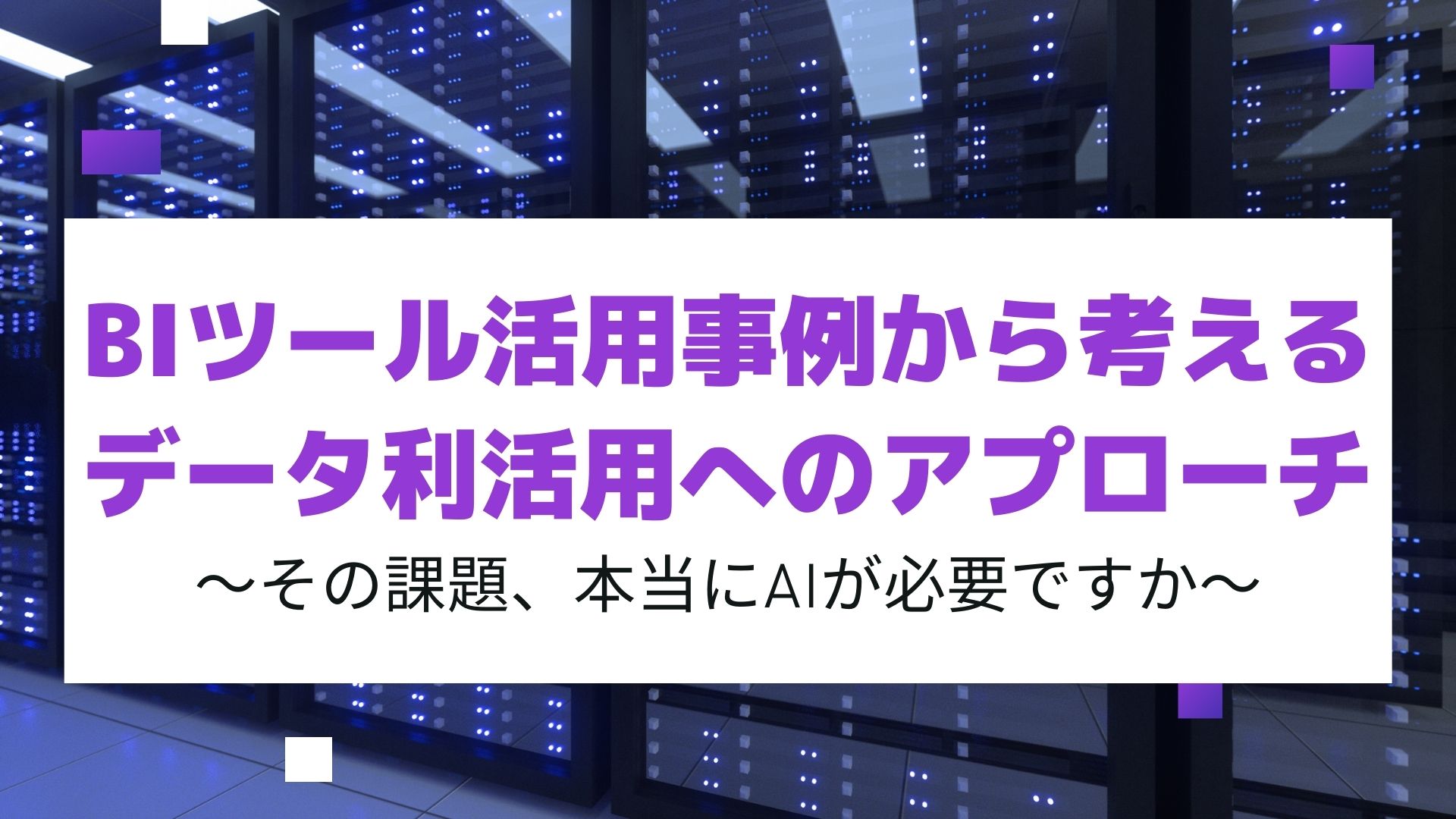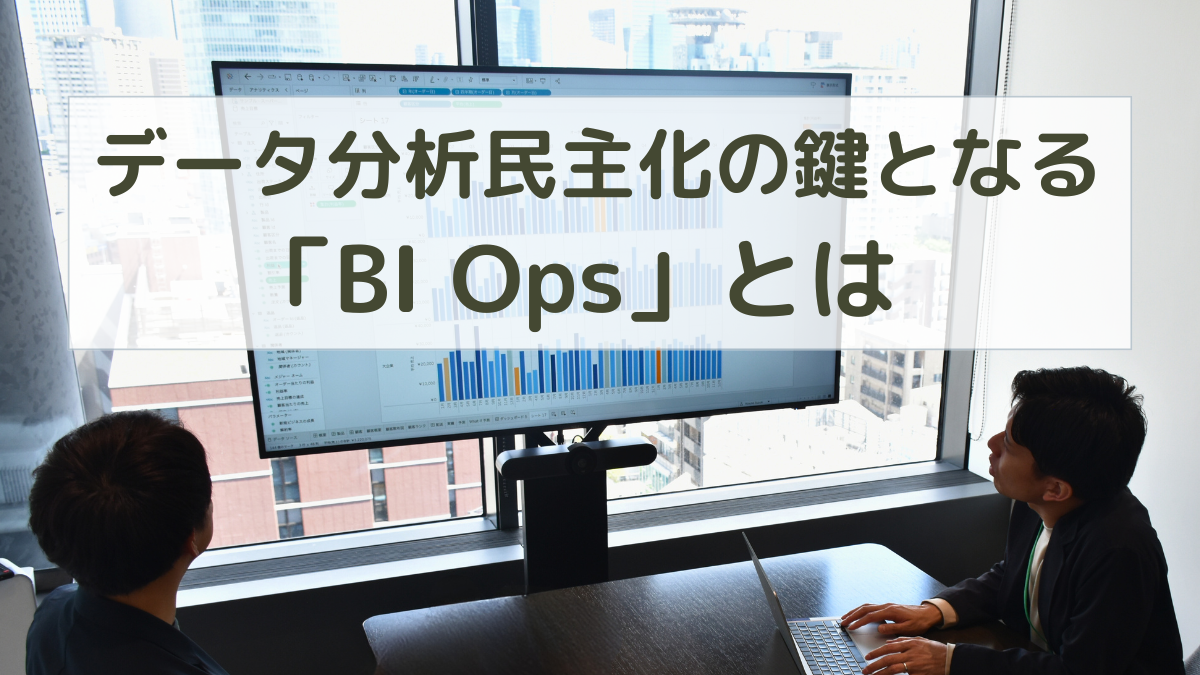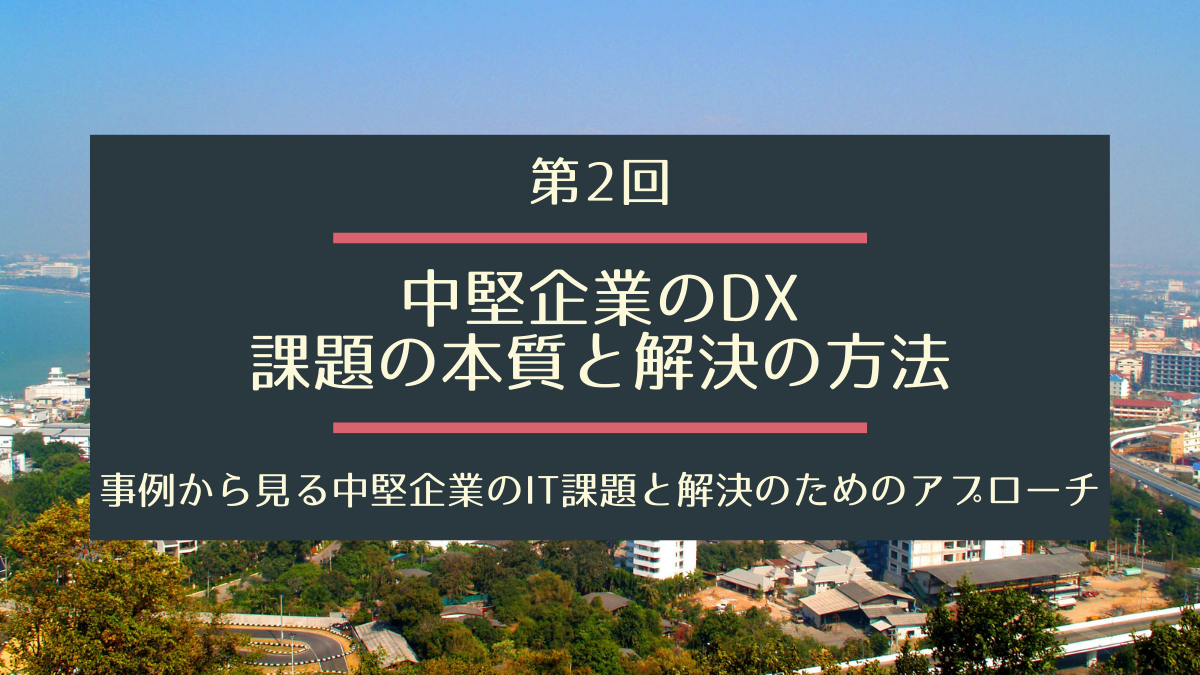DXなど変革プロジェクトでは『ビジネスアナリスト(BA)』が業務分析や変革手法の専門家として、ビジネス側とデジタル実装するエンジニアの橋渡しとなりプロジェクトを推進します。では、AI活用などを含むデータ分析プロジェクトの場合はどうでしょうか? プロジェクトの進め方から、データセットや使用するアルゴリズムの知識、課題に応じた分析手法を選ぶスキルなど、BAに必要な知識・スキルが大きく異なります。
そんな中、IIBA(https://japan.iiba.org/)がデータ分析分野のビジネスアナリスト(=ビジネスデータアナリスト)の専門性を定義したIIBA®-CBDA(Certification in Business Data Analytics)の資格を新たに設定しました。
今回は、このビジネスデータアナリシスの資格「IIBA®-CBDA」をいちはやく日本国内で取得したLTSのデータサイエンティスト兼コンサルタントの鈴木航輔さんに、この資格やビジネスデータアナリストの意義、試験内容について話を聞きました。

業務システムの開発・導入支援を経験した後、データサイエンティストチームに参画。金融・商社を中心に、データ利活用の促進を支援。最近では、デジタルマーケティング施策の企画・設計にも携わる。(2024年5月時点)
「意味のあるデータ分析」への第一歩 IIBA-CBDAがもたらす視点の変化
―――まずはCBDAについて聞かせてください。
データ分析の資格ですと統計検定などがメジャーですが、他のデータ分析関連の資格と比較したCBDAの特徴はどのような点でしょうか?
鈴木:
データ分析の資格ではAI の知識・統計の知識を問うものがこれまで一般的でしたが、CBDAはデータ分析とビジネスの関係性に主眼が置かれています。ビジネスにおけるデータ分析の目標どう設計するのか、どういう手法でデータを扱うべきか、データ分析の結果をビジネスに導入する時にどうコミュニケーションを取るべきか、といった分析業務で直面するビジネス上の問いを主題としています。
CBDAでは、データ分析プロジェクトの目的をどう設定すべきか、どういった目的に対してどのような分析手法を適用すべきか、などプロジェクト推進上の課題になりやすい部分での振る舞いが問われます。このような課題と対処方法を本で勉強することは難しかったのですが、CBDA がまさにこの領域をカバーしています。
データ分析プロジェクトに馴染みのない方でも、プロジェクトの各プロセスにおける懸念事項やステークホルダーをはじめ、全体構造の把握から学習できるので、ビジネスでのデータ分析についてスタートからエンドまで感覚を掴むことができると思います。

―――CBDA試験がカバーする領域で起きる問題が、データ分析プロジェクトではよく起きているということですね。
鈴木:
そうですね。例えば、ビジネス課題に対してデータの活用で解決をしていこうとなった時、「本当にそれは意味があるのか?」といったフィルターがあまりかけられないまま進んでしまうことがあります。その結果、意味のないデータ分析に時間を使うことになります。
私もお客様の社内でデータ分析を促進する取り組みをしていますが、「BI ダッシュボードを作って満足してしまい、継続した活用に乗らない、」といった課題が起きています。
このような意味のないデータ分析が起きないように、プロジェクト推進の現場では注意が払われており、どの課題を解決するのかの優先付けや、スコープとする部分・しない部分を決める等のアセスメントが入るケースが多いですね。

―――なぜそのようにデータ分析と実際のビジネス課題が分離してしまうのでしょうか?
鈴木:
データ分析担当者が、ビジネス課題とその背景、現在発生している事象を把握出来ていないからだと思います。
ただ顧客からの要望通りに数値計算を行う「集計屋さん」ではなく、分析プロジェクトをリードする立場からプロジェクトの全体像を把握していれば、「このデータ分析は本当に意味があるのか」「データ分析の手法は適切なのか」という問いに回答できるようになります。
私が現在参画しているプロジェクトでも、このようなスキルを習得することで、ダッシュボード作成時のテーマやプロジェクトの進め方について、説得力のある提唱が実現できると考え、資格取得に至りました。
CBDA受験対策と試験の実態
―――データ分析プロジェクトを成功に導くには、データ分析とビジネスの橋渡しとなるスキルが必要不可欠なのですね。実際にCBDAを受験されるにあたって、どのように対策されたのでしょうか?
鈴木:
まずはIIBA 公式ガイドブックの読み込みから着手しました。知識のインプットという面では、LTS分析事業部の業務とCBDAがマッチする部分が多く、学習期間は1か月程度でしたが、英文での出題形式にはやや苦戦しました。ひたすら英文に目を通して、問題演習を反復し、「この文言とはこの表現だ」と紐づけて整理することに努めました。
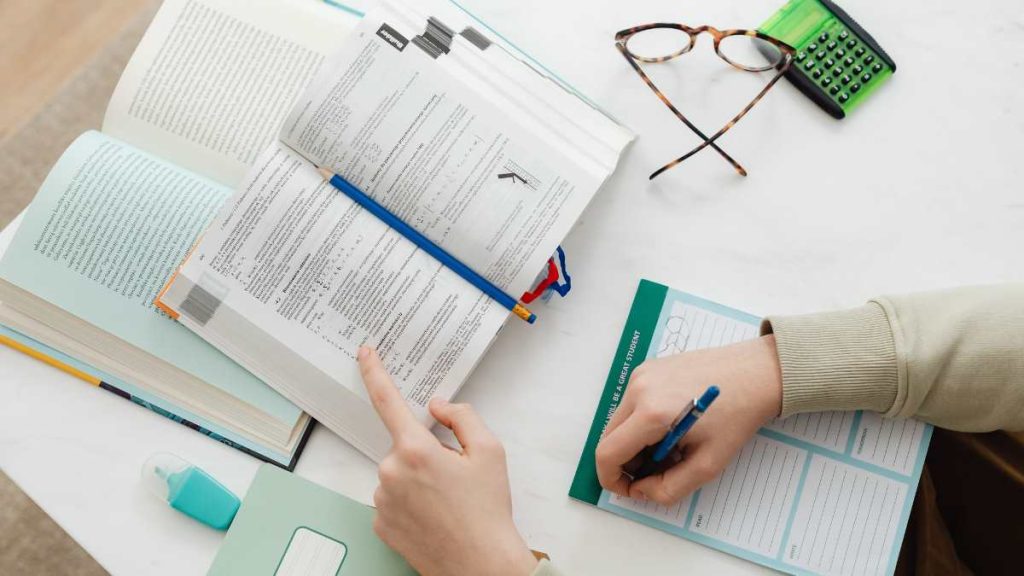
―――試験本番はオンライン方式かと思いますが、どのように実施されているのでしょうか?
鈴木:
試験はIIBA本部の試験官とテレビ電話を繋いでの実施となりますが、不正防止が徹底されており、初めにテーブルの上や部屋の中を、カメラで全部映すように指示されます。
部屋の中に誰もいないこと、手の届くところに本がないか等、細かい部分までチェックした上で試験開始となります。
試験時間中も、基本的に目立つ動作や独り言、退室も禁止されていますが、どうしても休憩が必要な場合は、専用のボタンから10分程度の休憩を申請することが出来ました。
―――IIBA主催の資格ということもあり、厳密な体制で実施されるのですね。
試験ではどのような問題が出題されるのでしょうか?
鈴木:
試験問題はテキストベースで、選択式での出題となります。
以下が出題例ですが、主にプロジェクトに適した分析手法やビジネス課題へのアプローチ方法が問われました。
<出題例>
・具体的なユースケースに沿った適切な分析目的の選択
・データの分散度合いを測るための手法
・データを可視化する適切な手法
・事例に合った適切な統計手法

DX推進担当者の可能性を広げるCBDA
―――CBDAではデータビジネスアナリストとしての基礎知識が出題されているのですね。
データ分析プロジェクトに携わる若手メンバーにとっても、良い勉強機会になりそうだと感じました。
鈴木:
そうですね。
若手メンバーにも資格取得を勧めていますが、各々の興味を尊重したいので、最終的には自身で意思決定してもらうようにしています。ただ淡々とデータ分析業務をこなすだけでは時間が勿体無いのでプロジェクト経験を有意義なものにするためにも、CBDAで問われるような適切な進め方や、ステークホルダーとのコミュニケーションには意識を向けてほしいと伝えています。
特にPM・PMOのような動きをするメンバーは、CBDAを通して、顧客・分析担当者・データ基盤担当者等の各ステークホルダーをマネジメントし、プロジェクトを円滑にする術を習得できると考えています。

―――CBDAはデータ分析プロジェクト経験者には勿論、未経験者にとってもキャリアの可能性を広げる契機になるのではないでしょうか?
鈴木:
勿論です。
それこそエンジニアとして分析業務に携わっている方であれば、いわゆる「分析屋さん」から脱却し、コンサルタントとしてプロジェクトをリードする立場にキャリアアップするための、契機になるかと思います。
また、事業会社でデータ活用を推進していく立場の方、DX推進担当者にもおすすめです。
「本当にこの分析には意味があるのか?」「分析手法はこうした方が良いのではないか?」といった疑問に答え、ベンダー・コンサルとの関わり方を理解できるようになります。ビジネスアナリストに近い位置づけでプロジェクトを進められるようになるので、自社のデータ活用に有益だと思います。
インタビュアー・ライター
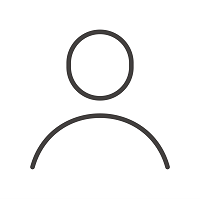
2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)