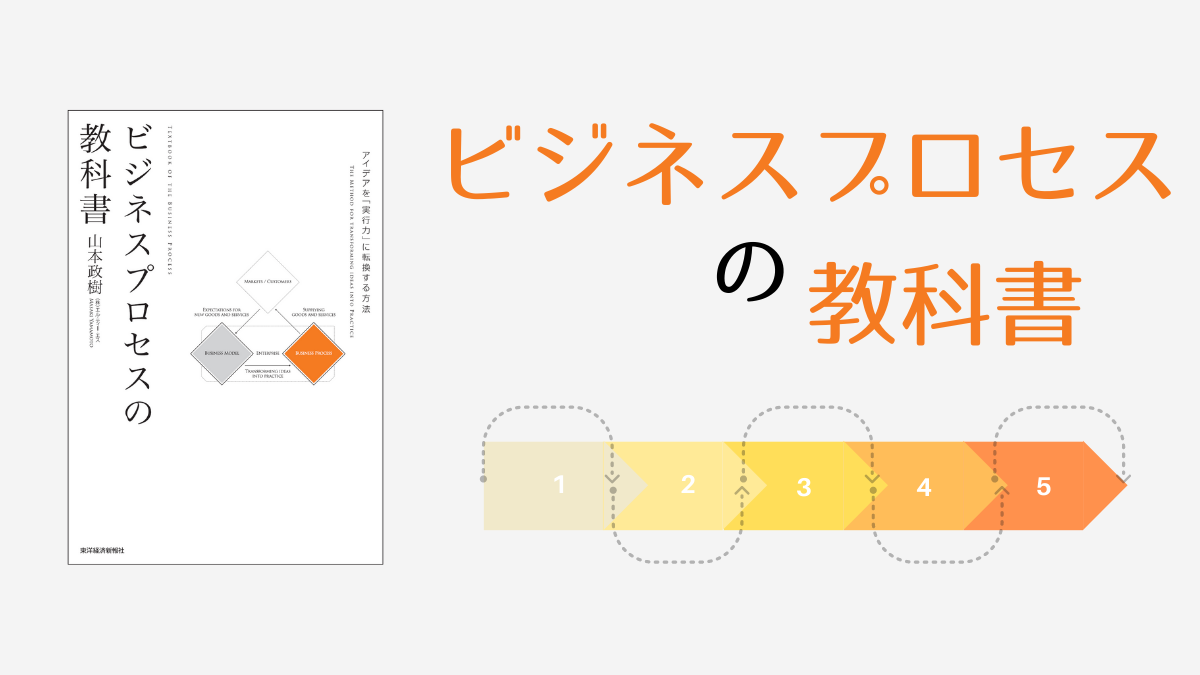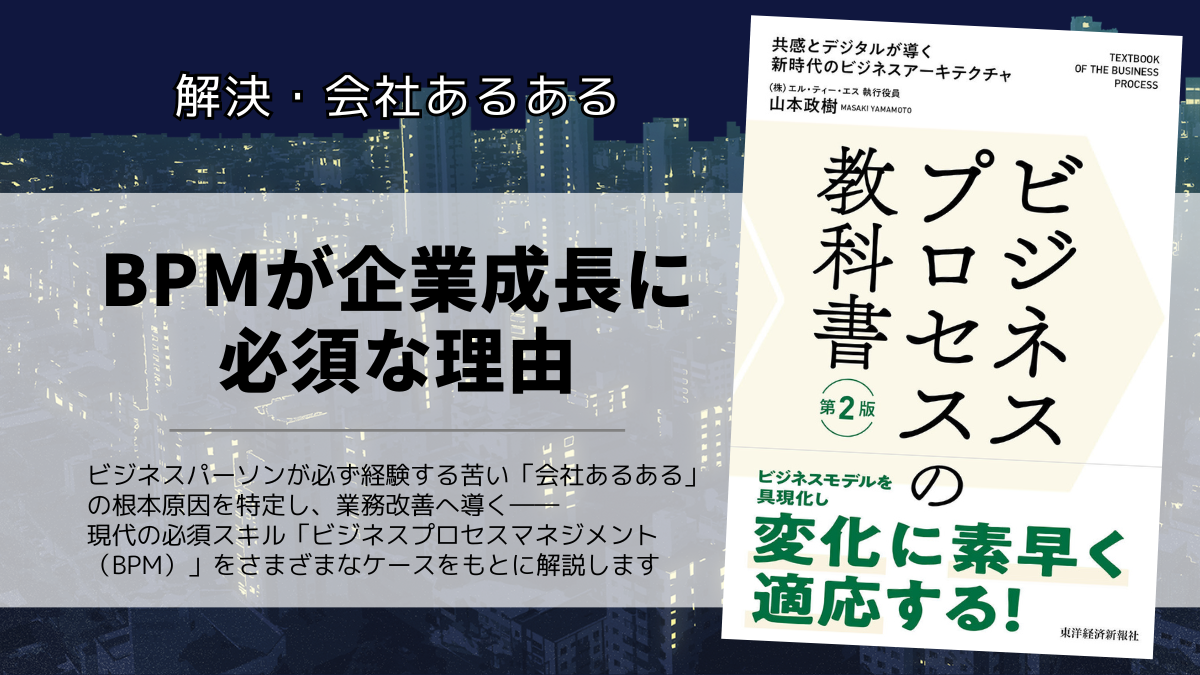※議論の成果は2026年に出版予定です。
たゆまぬ変革の指針「能力目標」
山本:
最初に、たゆまぬ変革を志向する企業ビジョンとして感銘を受けた例を紹介させてください。工場用工具などプロツールの卸売を手掛けるトラスコ中山株式会社です。ホームページに「中期経営戦略」(能力目標)を掲載しています。
「ありたい姿」実現のために
常に最高の利便性を提供するために優先するのは、売上や利益などの「数値目標」よりも、どんなチカラを持った企業になるべきかの「能力目標」であると考えています。
いつの時代もお客様や社会から必要とされる企業を目指していくために、以下の「ありたい姿」を掲げ、事業に取り組んでまいります。
「ありたい姿」を具体的かつ詳細に明示し、さらにそれを実現するために業務や組織も含めた全体プロセスをどうすべきか、未来像を描いているのです。
白鳥:
「能力目標」を定めることは経営の仕事そのものです。そして、これを実際の業務に適用し、ありたい姿を実現するのは今回のテーマ、「ビジネスの課題は何か?」「デジタルでどう解決するか」という観点から変革を進めるビジネスアーキテクト、ビジネスアナリスト(※1)の役割ということですね。

当記事では、ビジネスアーキテクト(ビジネスモデルやビジネスプロセス、組織などの仕組みを設計し、DX実現に向けてプロジェクトをリードする人材)やビジネスアナリスト(業務分析のスキルを活かし、企業の課題を分析し課題策を立案、実行する専門家)など、企業の変革をビジネス側から進める変革専門人材をビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材と表記します。
山本:
はい。業績目標は能力目標とセットで打ち出し、企業変革は経営が自分たちは「こんな姿を目指す」というビジョンを提示しない限り起きえません。その観点で、私はトラスコ中山の姿勢に感銘を受けたわけです。
そして、白鳥さんが先回りしてくれたように、変革にはビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材が欠かせませんが、日本では具体的に活躍しているケースは少数です。白鳥さんとは、この課題と解決策を掘り下げたいと思います。

スーパーマンは存在しない
山本:
生成AIなど急速な技術進展に伴い、DX推進に必要な5つの人材類型の一つとして「ビジネスアーキテクト」を経済産業省が定義(※2)したのは2022年です。普及はまだ緒に就いたばかりですが、白鳥さんは現状、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を含め日本のDX人材育成状況をどう見ていますか?
経済産業省が定義した、DXを推進する人材の役割と必要なスキル。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.html
白鳥:
DXを進めるために専門人材が必要であるという認識は浸透しています。実際、人材育成に関する引き合いも多く頂いていますし、上場企業であれば何かしらの取り組みをしていることがほとんどです。一方、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材という言葉も認知されつつあるものの、その職務・職能の解像度は粗い、また具体的なイメージは理解されていません。
山本:
そうですね。先日、SAPジャパンとLTSが共催した勉強会で解説する機会がありました。その領域に関心を持っているビジネスマンが集まりましたが、終了後「説明を聞くまで、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材が具体的に何をやる人なのかイメージを持っていませんでした」というフィードバックをたくさんもらいました。
白鳥:
この2、3年で流行したノーコード/ローコードによる市民開発が誤解を招いていることもありそうです。ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材は存在しても社員の1% 程です。これを説明すると「そんなに少ないのか」というリアクションが多いのです。1%もいれば十分なのですが、市民開発と混同され、現場に1、2人は存在すると思われていますから。

山本:
現場の改善と企業変革が混同されがちですよね。整理すると、個別のデジタルプロジェクトを成功に導くためのビジネスアナリストがいます。そして、各事業部門で目的は同じだけど異なるシステムが動いている時に、アーキテクチャ(システムやソフトウェア、ネットワークの全体的な構造や設計)という概念と、ビジネスアーキテクトが登場します。総じてビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材とは、ステークホルダーの合意を取り付け、組織横断の取り組みを実現するため、ファシリテーションを駆使して社内調整をする現場の枠を超えた専門職です。
白鳥:
そんな専門職にもかかわらず、DSSで定義されているビジネスアーキテクトの役割には、プロダクトマネージャーやイントレプレナー(intrapreneur。企業内で新規事業やPJ立ち上げなどの役割を担う人材)、デジタル実装のデザイナー、ビジネスアーキテクトやビジネスアナリストなど様々な役割が含まれていますね。幅が広いと感じますが…。
山本:
はい。端的に言うとスーパーマンです。これがビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材の解像度が粗い、具体的なイメージが理解されていない大きな理由だと思います。現状のDSSは、役割として「ビジネスアナリスト」を意図していますが、名称は「ビジネスアーキテクト」、そして必要スキルとしてプロダクトマネージャー、エンタープライズアーキテクチャ、ストラテジスト、マーケティング…が求められている、という状態になっているのです。
白鳥:
そんなスーパーマンは存在しませんね。もう少し、定義と必要スキルの整理が必要だと痛感します。

「実践の場」をどう確保するか
山本:
そこで、「まずはビジネスアーキテクトの役割を分解し、人物像、育成のイメージができるレベルで細かく定義しませんか?」と経産省に提言しているところです。(※3)
山本は、経産省の「『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』報告書:スキルベースの人材育成を目指して」のワーキンググループメンバーです。同検討会は、デジタルスキル標準や試験区分の見直しの具体化に向けて検討する取り組みです。

いずれにせよ、ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材を含めDX人材に関して言うと、白鳥さんが冒頭で指摘したように、育成に取り組んでいる企業は多いのですが、では成果が出ているか?と考えると、どうもそうではない。育成はしているけど、具体的なDXや応用につながっていない。あるいは現場業務が少し楽になった程度で終わり、企業変革という成果が出ないという結果に終わっています。
白鳥:
まず育成で言うと、先に指摘したよう人材像が理解されておらず、また実践機会が不十分です。ビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材は現場の改善活動に携わりながら、経営と現場の間で指揮をとるわけですが、企業のDX活動サイクルに組み込まれていないので、仮に育成したとしても活動の場がありません。
成果に関しては、紹介されたトラスコ中山のビジョン、「ありたい姿」が指針になります。多くの企業ではそもそもビジョンがなく、あっても不明確なので、変革の道具であるデジタル技術と融合できないのです。
山本:
市民開発で触れた現場の改善を担う人材は卵になるかもしれませんが、部門を横断した変革を担うビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材とはやはり職能が異なりますね。改善ではなく一定規模の変革、部門の壁を越えたそれなりに大きな取り組みができる「実践の場」が育成には絶対に必要ですね。
また、DSSで定義されたとは言え、ほとんどの企業ではビジネスアーキテクト/ビジネスアナリスト人材のポジションがありません。その具体的な職務内容をデザインし、処遇やキャリアパスをつくる必要があります。これについては、(下)で議論しましょう。
(下)<日本流「ビジネスアナリスト」のつくり方 人材市場とコミュニティがカギ>に続きます。
エディター・ライター
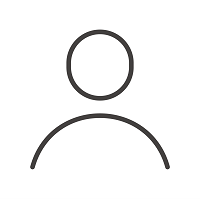
CLOVER編集部員。メディアの立ち上げから携わり、現在は運営と運用・管理を担当。SIerでSE、社会教育団体で出版・編集業務を経験し、現在はLTSマーケティングGに所属。趣味は自然観賞、旅行、グルメ、和装。(2021年6月時点)