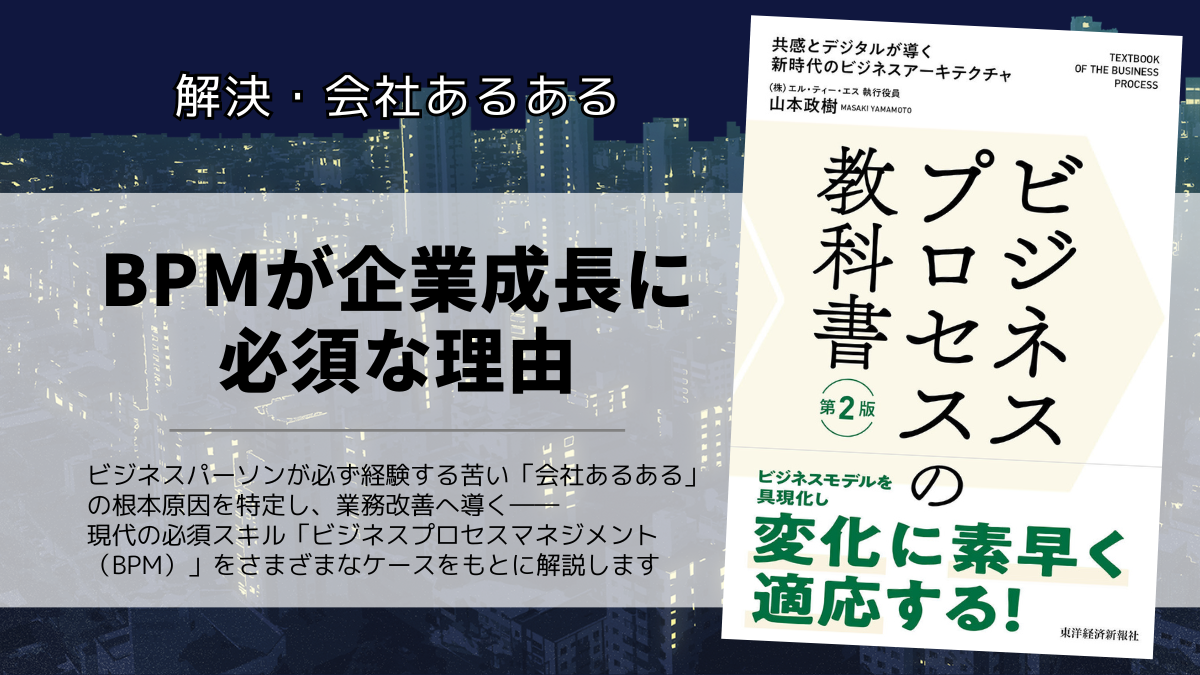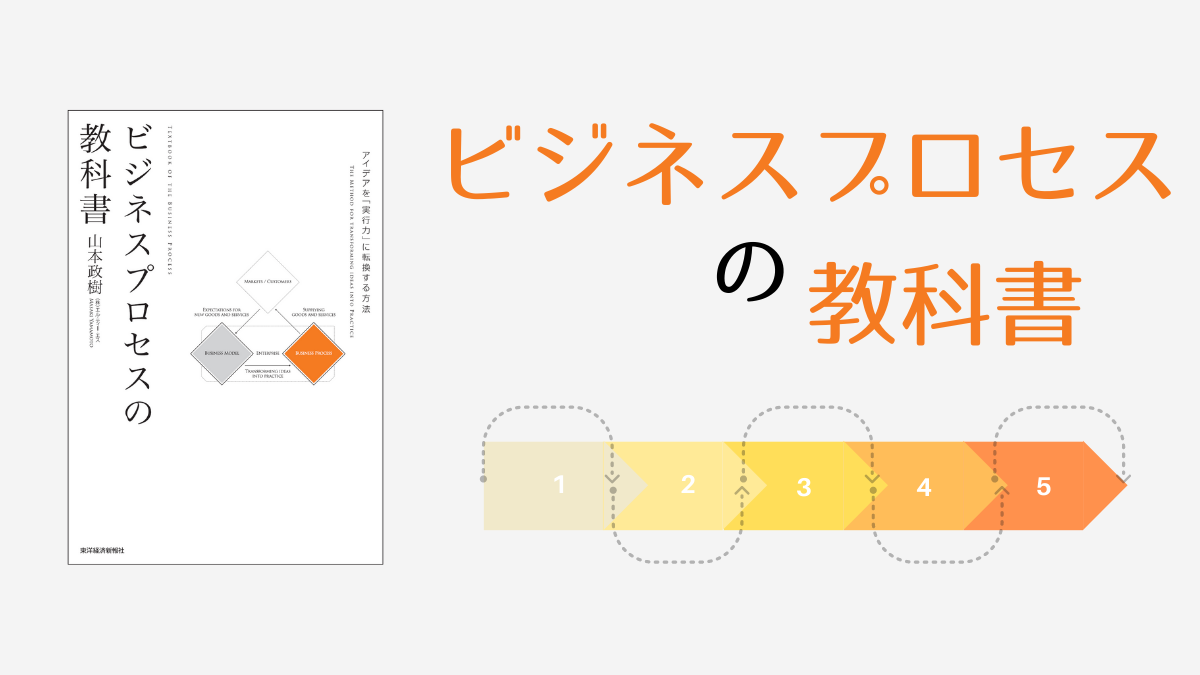このコラムは、株式会社エル・ティー・エスのLTSコラムとして2019年4月から連載を開始した記事を移設したものです。
当コラムの最新の内容は、書籍『Business Agility これからの企業に求められる「変化に適応する力」(プレジデント社、2021年1月19日)』でご紹介しております。
ライター
様々な観点から見る ビジネスアジリティの“以前”と“以後”
こんにちは、LTSの山本政樹です。
前回の「ビジネスアジリティとは何か」の前編では、ビジネスアジリティの定義と概観をみてきました。企業が“アジリティを持つ”とは戦略、ビジネスアーキテクチャ、組織構造など組織内のありとあらゆる要素で、様々な能力や仕組みを複合的に保持する必要があります。ですから、以下では各要素別にビジネスアジリティ以前の世界と、以後の世界で何が違うのかを考えてみました。全部で7つの観点で「ビジネスアジリティを重視すると各要素がどう変わるのか」ということを解説しています。次回以降、この要素ごとにより詳しくビジネスアジリティを解説していきますが、今回はまず全体を俯瞰して理解頂ければと思います。
戦略~正確だが遅い判断から、迅速で常に軌道修正する判断へ~
過去は「戦略策定」とは情報を正確に分析しその延長線上に推測できる未来から、全てにおいてしっかりとした計画を立てて着実に実行していくことが中心でした。この前提となっていたのは、失敗や撤退はマイナスとされ全てにおいて確実性が重視される思想です。しかし、変化が日常化する世界においては、手元のデータで頑張って予測してみても明日世界が同じルールで動くとは限らないのです。このような時は、机上で考えることに多くの時間を使うより、行動してみて現実世界の中でそれが機能するか確かめてみる方が早いこともあります。スピード感を重視した決定で「まずやってみる。そしてダメだったらすぐに戦略を修正する、ないし撤退する」というのが、これからの経営判断に求められる姿勢になります。
このような経営判断を行おうとすると、今この時お客様はどのように行動しているのかといったリアルタイムでより現場に近いデータが重みを増します。これまでのような月次の売上・利益などの財務データは、お客様の購買行動が反映されて集計されるまでにタイムラグがあります。顧客動向のようなリアルタイムの情報から変化の兆しを見つけ、先ほどの事業戦略修正(ないし撤退)の判断を機動的にまわしていくのです。
財務~資産は保有するものからアクセスするものへ~
過去、資産は所有することに意味があると思われた時代がありました。「土地神話」などが代表例ですが、これらの神話を信じた会社は1990年代のバブル崩壊で大損害を被りました。変化が速い時代では現在持っている資産が将来において同じ基準で価値を発揮するとは限らず、むしろ負債となる危険性すらあります。このようにNPV(正味現在価値)的な考え方による資産価値の判定だけでなく、“リアルオプション思考”と言われるように、資産の用途転換や売却等の容易さを考慮した資産選定が大切になるでしょう。資産価値自体は低くても、環境が変わった時に他の選択肢(=オプション)を持てる資産の方が、より価値が高いという考え方です。
そもそも資源自体を所有するという考え方自体が、変化に適応する上でのブレーキとなることもあります。資源はあくまでも事業で価値を産むためのツールです。必要な時に必要な分だけ使えればよく、クラウドやアウトソーシングといった、取り込みやすく切り離しやすい資源の活用が進むと思われます。
ビジネスアーキテクチャ~事業構造の“ビルディングブロック”を管理する~
いくらスピード感をもって戦略を立案することが出来ても、ビジネスアーキテクチャへの戦略の落とし込みが速やかに進まなければいつまでもたっても戦略は実現されません。ビジネスプロセスが構築され、オペレーションが可能になってはじめて、製品やサービスという形でお客様に価値が届くからです。ビジネスアーキテクチャにおけるビジネスアジリティとは「意思決定に従って速やかに意図されたビジネスプロセスを作り上げ、お客様に製品やサービスを提供可能にするための能力」がその中心となります。
ビジネスアーキテクチャ(=事業構造)が変化に柔軟に対応できるとは、どのようなことでしょうか。これには組織を構成する要素、つまり「ビルディングブロック」をしっかり識別し管理することが大切になります。ビルディングブロックにはビジネスプロセス、ルール、組織、情報など様々な要素が含まれますが、中でも社内に存在するプロセスの管理はその作業の中心です。何か変化が必要となったら、影響を受けるプロセスを速やかに特定し、新しいプロセス(=新たなブロック)に交換していくのです。これを可能にするためには個々のプロセスの範囲、隣接するプロセスとの境界、プロセスオーナーなどが明確になっている必要があります。過去はこのような構造管理は変革を実施する際の一時的な作業として行われるものでしたが、変化が日常となる世界においてこれらは変化に備えるための日常的な作業となります。
テクノロジーアーキテクチャ~ビジネスとエンジニアリングが一体となる~
テクノロジーアーキテクチャもビジネスアーキテクチャと同様に、ビルディングブロックを普段から管理し、変化の際には容易に識別、変更できるようにしておく必要があります。テクノロジーアーキテクチャにおけるビルディングブロックとは個々の情報システムやネットワーク、サーバーといったシステム構成要素と考えれば良いでしょう。入れ替え容易なブロックにしておくということを考えると、必然的にクラウドやパッケージソリューションの活用は重みを増します。自社で開発するツールも構造をしっかり管理し、BPMS等の開発ツールを駆使しながら速やかに改修が可能な構造としておくべきです。もちろん、ベンダー任せで自分たちでは仕様が分からないなどというのはアジリティのある状態ではありません。
またビジネスの要求を、エンジニアリング側がいちいちゼロから理解して実現するという流れでは時間がかかりすぎます。普段からビジネスとエンジニアリングの一体感を醸成しておき、ビジネス側の問題意識や業務の状況をIT部門のようなエンジニアリング側も理解しておくことで、いざ取り組みを開始する時には速やかにチームを組成することが出来ます。
組織~階層型組織から、フラットでネットワーク型の組織へ~
アジリティを重視すると組織はフラットになります。これまでの階層型組織ではトップの意思がいきわたらなければ組織が動かず、そして現場の実態や問題がトップに伝わるのに時間がかかってしまいます(というよりそもそも伝わらないこともあるでしょう)。フラットでネットワーク型の組織では、個々の組織構成員が指示や命令を待たずに目の前の課題に対して自律的な判断で動きます。指示がなくてもおかしなことにならないのは、普段からのコミュニケーションで組織のミッションやビジョンに対しての合意があるからです。
変化に対応するために必然的に組織改訂は頻繁になりますが、組織が変わってもビジネスプロセスが安定的に機能するためには、組織とプロセスの認識を分離し、それらの紐づけをしっかり管理する体制が必要となります。その意味では前述のビジネスアーキテクチャも、円滑な組織運営のための大切なツールとなります。
人~均質で平等な世界から、個性を活かし皆が異なる働き方をする世界へ~
アジャイルな世界が組織に所属する人に及ぼす影響は大きなものです。これまでの企業における社員はもっぱら安定かつ継続的な仕事に従事し正確に作業をこなすことが求められました。しかし、このような作業はどんどん機械(ITやロボット)にとって代わられます。
一方で変化を生み出し実現することが人の役割となります。皆が同じことをやるのではなく、それぞれが異なる専門性をもってお互いの力を補いながら価値を創造します。そして、まだ見ぬ世界にチャレンジし、失敗から学ぶことが奨励されます。個々人が異なる専門性を持ち、様々なことにチャレンジにまい進する中では「公平で平等な評価」などは意味を持ちません。置かれる前提が違いすぎるので、客観的な基準に照らすのではなく関係者の主観に基づいた相互尊重という形で評価をすることになります。ある意味で、人と人とが直接つながる原始的な社会への回帰といえるかもしれません。
このような世界はわくわくするものではありますが、一方で人は基本的に安定を求める性質があることも事実です。変化からくるストレスを前向きな想いに転換していく“レジリエンス”は必須な能力となるでしょう。
変革活動~一過性の大変革だけではなく、大小の変革が日常化する世界へ~
過去、企業を変えることは一過性の大仕事でした。数年から10年単位で大きな取り組みが組織され、綿密な計画と徹底した調整のもとプロジェクトは進められました。しかし変化が恒常化してしまえば、このような「変化の時と安定の時」といったような分類は意味を持ちません。変化は日常化し、常に大小様々な変革が行われる世界になります。変化に際して全ての関係者が合意するまで活動を待つことも難しくなります。責任範囲を明確にし、全体の合意を待つのではなく各領域の責任者がより主体性をもって変革を推進して行くことになるでしょう。また、説明責任は変化を起こす側だけではなく、変化に反対する側にも生じることになるでしょう。「活動に納得できないから協力しない」では済まされず、なぜその活動を行うべきでないかを周囲に納得させる責任が生じるということです。
このような世界では、日常的な変革活動を支えるプログラムマネジメント組織や、これらの活動に恒常的に従事する変革専門人材が必要になります。現実問題としてオペレーションと変革活動の両立は年を追うごとに難しくなっています。変革専門人材を置くことは、オペレーション人材と変革活動を分離してしまうことを意味するものではありませんが、状況に応じて、オペレーション人材が兼務で変革活動を実施するのか、変革専門人材に主体を任せるのか、という判断をする機会は増えるでしょう。
組織運営の考え方は徐々に、しかし着実に変わっていく
ここまでざっと、これからからの企業が持つビジネスアジリティの姿を見てきました。簡単にまとめてしまえば、高いビジネスアジリティを持った企業では、速い意思決定の下、常に替わる方針の下で、異なる専門性を持った人材が協力し合いながら自社を変える活動に従事しています。また会社の基盤として、このような変革活動を支えるための業務管理基盤やコミュニケーションインフラも整備されています。
ただ、ここで紹介している姿はかなり極端な姿であり、決して明日から全ての企業が突然ここに書かれたような全く違う姿に変異するわけではないということです。業界や業種によっても変化のスピードは異なります。一企業の中でも変化が早いサービスも、これまで通りの価値提供を当面の間は着実に続けなくてはいけないサービスもあるでしょう。このような変化は既に起きているものでもあり、これから起きるものでもあり、あるところでは当面は起きないものであるのです。
正直に言えば、各種のカンファレンスやマスコミの記事など、オピニオン発信の場で言われる「変化の早い時代」は誇張されており、特に変革関連のサービスに利害のある人たちが無闇に変化への対応を煽っているとみられる部分があります。「変化させないといけない」という意識にとらわれすぎて拙速に走った結果、破たんしたサービスや企業の事例もたくさんあります。また、破たんとまで言わなくても拙速で失敗するデジタル技術導入のプロジェクトなどは山のようです。
ですから紹介したような考え方は、皆さんが直面する個々の局面で常に適用されるわけではないということも理解しておいて頂きたいと思います。これまでの価値観とこれからの価値観、その両方を理解した上で自分が今どのような規範に基づいて行動すべきかを判断することが大切になります。
とはいえ、全体としてはこのような変化は着実な流れでもあります。既に多くの企業に変化が、適応するためのビジネスアジリティを育てる活動を始めています。次回からは、今回のコラムで簡単に紹介したビジネスアジリティの要素ごとに、より詳しく事例などを交えながらビジネスアジリティを持つとはどういうことかを紹介していきたいと思います。
ここまで読んで頂きありがとうございました。次回以降もご期待ください。