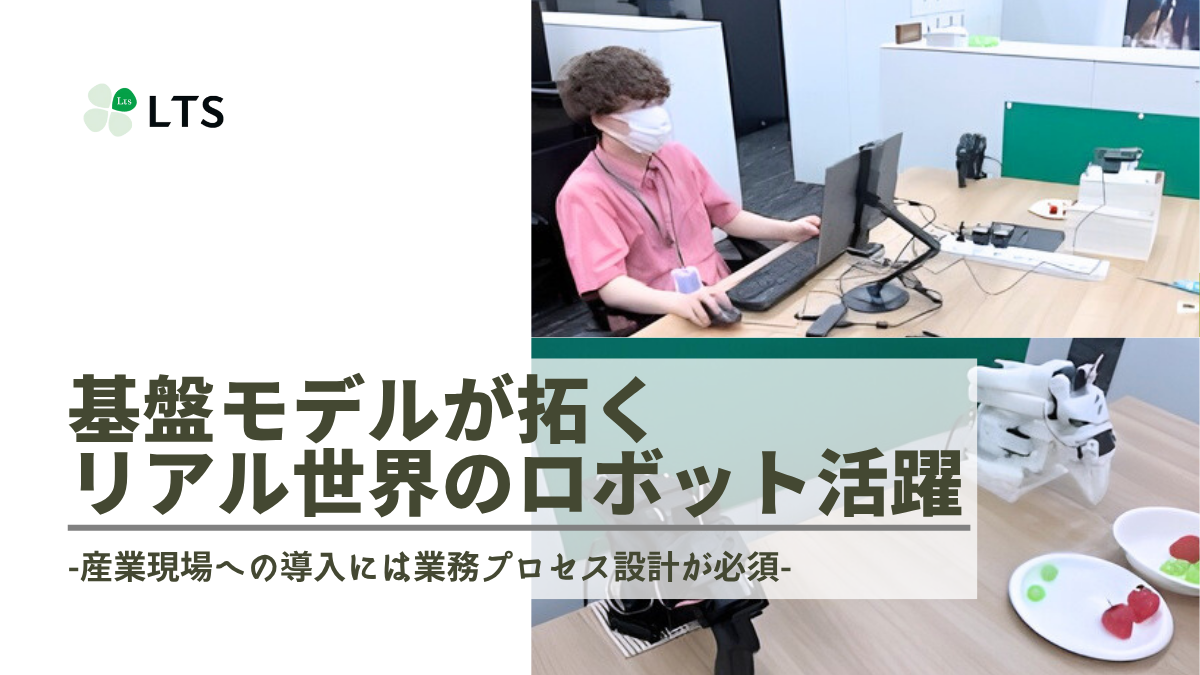今回は、対談で語り切れなかった背景や、デジタルを前提とした社会で企業や経営層はどのようなスタンスで臨むべきか?について、引き続き両名に話を聞きました。

DXのボトルネックはアナログのままの経営陣や評価指標
亀本:
DXは手段であるものの、企業が取り組まないといけない課題という側面もあります。当たり前のようにデジタルデータが溢れていて、過去に類を見ないレベルで企業と消費者がつながっている。そういった大きな変化に、従来型の経営者は追いつけていません。
今回の記事で伝えたかったことは、こういった社会変化と経営のスタンスに対する危機意識です。

「会社として健全な状態を保つ」という経営者の考え方の根幹にある思想そのものを、デジタル時代に合わせて変える必要があります。ですが、過去の成功体験を持っている年代の経営者の方々はPL思考が強固で、管理会計の考え方も会社としてのKPIも過去にとらわれています。
一番違和感があるのが「利益創出を企業活動の第一義的な目的」とした考え方です。
企業の目的は、あくまでもパーパスやミッション・ビジョンの達成です。そしてそれを実現するために、企業活動を続けられる体力やブランドが必要(ゴーイングコンサーン)、ということは共通理解だと思います。一方で、ゴーイングコンサーンを実現するための手段が「利益をあげる」ことだけなのか?というと、そうではなくなってきていると考えています。
企業と顧客が「一方的にモノを造って売る」という関係性にとどまっている場合は、たしかに利益をあげることが唯一の企業が生き残るための手段であるかもしれません。しかし、顧客とダイレクトにつながり、ある程度先の売上も確度高く見込めている企業にとっては、その「つながり」を担保にファイナンスすることもできるようになっています(事実、リカーリング収益を担保にデッドファイナンスを行うサービスが出てきています)。
けっきょくPLを良くすることで喜ぶのは、一部の株主や親会社・ホールディングス会社です。もちろん、それらも大事なステークホルダーの一部ではありますが、それと並ぶ重要なステークホルダーである「顧客」に意識が向かっていません。「モノ売りからの脱却」は多くの企業でテーマとなっていますが、本当にそれを実現したいのであれば、例えば「5年後の累積黒字」などに評価指標を据えることはまったくのナンセンスです。それよりも、本質的に「顧客」にとっての価値を高めるために日々お客様とコミュニケーションをしながら、より良い価値を提供し続ける仕組みを創っていくことが経営の役割であると考えます。
デジタル時代だからこそ、顧客の声を直接聞ける場所でビジネスを
亀本:
もう一つの問題提起として、日本の物売りは「代理店ビジネス」が多いですよね。大手のメーカーはこの時代になっても「作るだけ作り、自分達のプロダクトアウトの考え方でものの研究や投資をし、それを作っていない代理店の人たちに持って行かせる」ということをやっています。代理店が商品をお客様に売るのですが、そうするとメーカー側は顧客接点を持っていないわけです。お客様と直接対峙するコミュニケーションの姿勢がないままで、どうやってお客様との間のブランド価値を作っていくのでしょう。
代理店販売モデル自体を否定するつもりはまったくありません。しかしポイントは「メーカーは造るだけが仕事なのか?」というところです。顧客との「つながり」が経営を左右するのであれば、それを外部のパートナーに渡してしまっていいのか?それこそが自社でしっかりと握っていなくていけないコアの活動であるはずです。ビジネスを伸ばしているメーカーはこれをよく理解しており、自分たちの機能の中に「カスタマーサクセス機能」をしっかり構築して、お客様と対峙しながら要望を聞きサービスの価値を上げています。この点、日系のメーカーは遅れていると考えます。
日本では、企業内外にある機能を迅速・柔軟に変更できないというジレンマがあるように思います。グローバルでスピード感のある企業やスタートアップと比較するとビジネスモデルとプロセスを変えるスピードがきわめて遅く、移り変わりの早いこの時代において競争力を担保できる状態になっていません。企業が変化に対応できるアジリティのある体制やそのためのKPIを設計してくことが大事です。
実はこういった問題を解決する方法の一つがDXではないか?と自分は思っています。単純な業務効率化を目的としたDXが目立ちますが、その手前として「企業がどのようにデジタル時代に立ち向かっていくのか? 社会や顧客との関係の変化をどのように捉え企業の経営側がどうやって向き合っていくのか?」を考えるのにデジタルの活用を必ず前提として考えてほしいです。
今回は「手段としてのDX」のテーマをスタートとして話しましたが、こういった「前提としてのデジタル」という考え方も伝えていきたいと思ってます。
デジタル時代のプロダクトアウト
亀本:
マーケットインとプロダクトアウトを例に考えてみます。
新規事業開発の場合、最初に市場があるか? 次に消費者のニーズがどの程度あるか? そしてその中で取れるシェアがどの程度でどのくらいの売上を見込めるか? を考えます。その後に、ではどの程度投資をするか? まで考えて事業計画を作ります。これは典型的なマーケットインの考え方です。
このマーケットインのモデルを否定するつもりはないのですが、デジタルが社会の前提となる現在はそれ以前と比べてプロダクトアウトの考え方が求められているように感じています。
消費者と自分達作り手・売り手の関係が変化しているのです。自分達と消費者を、価値を提供する側・される側として捉えるのではなくて、自分たちのエンジニアリングチェーンの中に双方が組み込まれているイメージです。デジタルで作り手と使い手の距離がほとんどゼロになり、サプライチェーンの最後に消費者がいるのではなく、エンジニアリングチェーンの真ん中に消費者が入って来ているのです。
デジタルを使った顧客との常時接続のコミュニケーションを前提とすると、マーケットインの「ニーズを確認して投資を計画する方法」からもっとスピード感があるやり方に変わっていく必要があると思います。それは顧客をプロセスに組み込んだ新しいプロダクトアウトのモデルかもしれません。
外の世界とシンクロしてデジタル化の理想を形にする
山本:
製品開発の「発想の仕方」が変わったということだと思います。

従来のプロダクトアウトの製品開発は「自分たちが作りたいもの、作れるものを作る」でしたが、最近の製品開発は「外の世界に自分達をシンクロさせる」ことで、ある意味消費者と一体化している状態が発想の原点になっています。自分が「これが欲しい!」と思ったものがまだ存在していないこと、それが原動力になっているんです。
スティーブ・ジョブズも似たような思想だったのではないでしょうか。自社にできることだから作る、こういうものがあったら売れる可能性があるから作る、ということではなくて、徹底的に自分がユーザー側に立つことから始めます。社会やユーザーとシンクロできる立場に自分を置いたときに感じる「こういうものが欲しいのに無い」という渇望からモノを作っていて、そのやり方は自分の発想が基礎にあるのでプロダクトアウトではあるものの、実際は社会やユーザーの隠れた不満を押さえているという構図になっています。
自分が社会やユーザーといった「外の世界」にうまくシンクロできていれば、自分が思ったことは外の世界全体が思っていることとイコールになります。この状態はこれまで以上にプロダクトアウトではないか?という逆説になり、そう考えるとマーケットインという考え方は、ある意味自分と外の世界のシンクロがうまくいかず、分からないから調べに行くという発想ではないでしょうか。そこにベクトルの逆流のような状態が発生しています。
発想として「これができる」ではなく「これが欲しい」なんです。自分はこれができるからモノをつくるプロダクトアウトはもう通用しませんが、自分はこれが欲しいからとにかく作る!というプロダクトアウトからは正解に近い製品やサービスが生まれるかもしれません。
DXを目標として捉えていると、デジタルを考える前提の視界が自分達の組織やビジネスの内側になってしまいます。すでにデジタル化している社会やユーザーを前提とした思考がやりにくいということです。
経済産業省のDXの定義でもデジタル化は目標の一部になっていますが、DXの定義を目標と事象どちらに重きを置くのかというと、自分は事象として捉えた方がいいと思っています。
事象としてのDXの捉え方が先にあり、その結果はじめて「自社としてDXをどう捉えるか?」という目標を描けるようになります。外の世界を広くとらえて、その中に自分達をシンクロさせていくという発想で、デジタルトランスフォーメーションを進めてほしいと考えています。
ライター

SE・テクニカルライターを経て、LTS入社。ERP導入や業務改革におけるユーザー向け広報・教育企画および業務文書改善など組織コミュニケーションに関連するコンサルティングに従事。2017年よりLTSコンサルティング事業のマーケティングを担当。2021年より本サイト「CLOVER Light」の立ち上げ~運営・編集長を務める。(2024年1月時点)