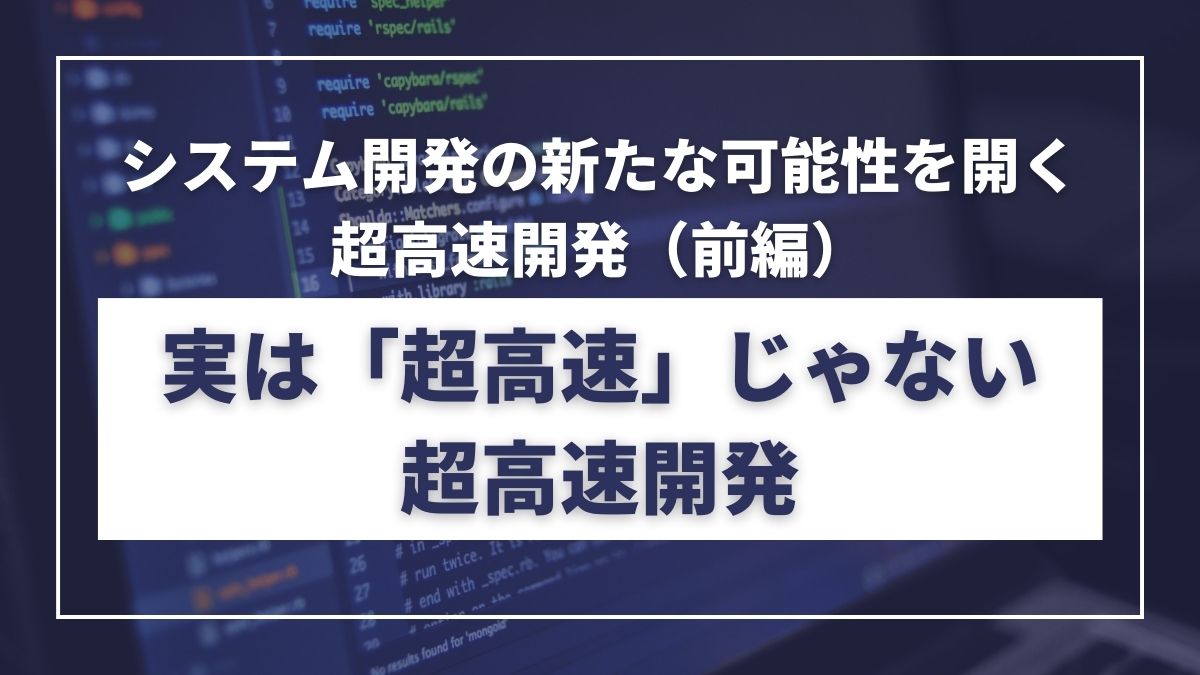これからの経営者に求められること
ここまで述べてきたように、これからの企業活動はこれまで以上にお客様と、そしてその先の社会との関係性の構築を意識することが大切になります。このような社会の変化をもたらしたものがデジタルであり(事象としてのDX)、そして関係性をマネジメントしていくために自社としてもデジタル技術を活用していく必要があります(目標としてのDX)。このコラムの最終回として、企業の経営者はDXにどう向き合うべきなのかを考えてみましょう。
企業経営者は自分をデジタル化した社会にシンクロさせなくてはならない
デジタルによって変わる社会を捉えて自社の在り方を描く
なぜ最初にDXを事象として捉えるべきなのかをあらためて振り返ってみると、それはDXを企業活動の一部として捉えてしまうと、すでにデジタル化している社会やユーザーを前提とした思考が働きにくくなってしまうからです。DXを企業目標として捉えてしまうので、デジタルを考える前提の視界がはじめから自分達の組織やビジネスの内側になってしまいます。ですから、まず「事象としてのDX」の捉え方が先にあり、その後にはじめて「自社としてDXをどう捉えるか?」という目標を描けるようになります。
この考え方は、誰よりもまず企業の経営者に求められるものです。経営者の方は、外の世界を広くとらえて、その中に自分達をシンクロさせていくという発想を持ってほしいと思います。デジタル技術をどう活用するかという命題は企業のDXのごく一部の問いでしかありません。大切なのはデジタルによって大きく、しかも劇的に変わる社会において、自社の在り様を描いて変革(=トランスフォーメーション)させていくこと、そしてそれを継続していくことです。
そう考えた時、経営者の方のDXに対する理解には不安を覚えることが多いのも事実です。
新技術を導入することが経営の「目的」ではない
「若手データサイエンティストが集まる会で、人工知能(AI)をテーマに講演をする機会があった。講演後の雑談で「会社の上層部から『なんでもいいからビッグデータを集めて、AIでなんとかしろ』と言われて困っている。そんなのは幻想だ、と言ってもらえないか」と頼まれた。」(2016年9月8日付日経産業新聞)
これは国立情報学研究所教授で東大合格を目指したAIロボット「東ロボくん」の開発を手掛けた新井紀子氏が、新聞のコラムで述べていたことです。日本では新しい技術が世に出てそれがブームになると、新技術を導入すること自体が目的化する傾向があります。技術が自社のビジネスにどのように役に立つのかよくわからないまま、最新技術を導入しさえすれば何か良いことが起きるだろうという曖昧なイメージで取り組みが進んでしまうのです。これは2000年前後のインターネットブームからはじまって、ERPやCRMの導入ブームなど常に同じことが起きてきました。2010年代半ばにビッグデータがブームとなった当初も、ビッグデータ活用の課題は「導入する目的の明確化」が一位となっています。
このような現場が混乱する指示を経営者が出してしまう背景には、技術に疎い経営者がDXというキーワードに、大変大げさな、言い換えれば夢みたいな幻想を抱いているということがあります。結果的に先ほどのような「とにかくAIを使ってなにかを取り組みをしろ」といったような乱暴な指示が出されます。名経営者やオピニオンリーダーと言われる人ですら、そのAIに対する言説を聞いていると「この人は本当にAIの動作原理を理解して話しているのだろうか」と心配になることは多いのです。多くの場合は華やかな活用事例や将来の展望ばかりに気を取られ、基本的な動作原理やリスク、技術的な限界を十分に理解していません。
経営者が自らデジタル社会に身を置き学ぶ姿勢が必要
全体的に大企業の経営層の中心にいるシニア世代は、デジタル化された社会の常識についていけているようには見えません。我が家(山本)では先日、こんなやりとりがありました。学校から帰ってきた息子が「今日は友達と遊ぶ」と言います。こちらが「いつ(家を)出ていくの?」と聞いたら、「コロナがすごいから、今日は家からオンラインでする」と言うわけです。その後、息子はヘッドセットで友達と通話しながらゲームを楽しんでいました。子供たちはもはや音楽もAIスピーカーできくものだと思っているみたいです。「アレクサ、YOASOBIの群青をかけて」といった具合です。子供たちは急速な勢いで、デジタルに習熟していきます。
小学生がこれですから、経営者がオンライン会議のセッティングを部下に任せるとか、話になりません。息子はコロナ蔓延化でも、会議室にすし詰めになって会合をしている政治家たちのニュースを不思議そうな目で眺めています。
経営者はまずデジタルが浸透した社会の姿に自分自身をしっかり置きましょう。お客様が使っているアプリ、従業員が使っているシステムを使ってみましょう。デジタルコミュニケーションを通して情勢される社会の価値観の変化に身をさらしましょう。AIについて知りたければ、ベンダーの担当者を会議室に呼んで経営者向けにアレンジされた壮大な話を聞くよりも、書籍などを活用して自ら勉強する方が早いです。今時、雑誌の付録で簡単なAIを自分で作ってみることもできます。「そういうことは若い従業員に任せる」だけではだめです。新しいことを自ら学ぶという姿勢を示すことができないのではあれば、もはやそれは今の時代の経営を担うリーダーの姿ではありません。
もはや意味のない「マーケットインか、プロダクトアウトか」という問い
従来の製品・サービス開発は「自分たちが作れるものを作る」という思想であり、これを「プロダクトアウト」と呼んでいました。一方で、市場調査やお客様の声を元に、「(市場から)求められるものを作る」という思想を「マーケットイン」と呼びます。この二つの思想はこれまで対立軸で語られ、総じて「プロダクトアウトからマーケットインへ」という流れで説明されることが多かったように思います。
しかし、マーケットインが正解かというとそうとも言えません。製品やサービスの機能的価値がお客様の理解を超えて高度化した結果、お客様も自分が製品やサービスに何を求めているのかを表現できなくなってしまったためです。そのため、市場調査の結果を額面通りに信じた製品を開発した結果、市場に出してもまったく売れなかったということも頻繁に起きるようになります。このような流れの中で、むしろ製品開発者の主観や想いを重視する「プロダクトアウト回帰」とも言える動きも起きています。
では本当は、プロダクトアウトとマーケットインのどちらが正解なのでしょうか。これに対する私たちの答えは明確です。自分たちが作れるものを作るプロダクトアウトも、主体性なく市場に解を求めに行くマーケットインもどちらも不正解です。しかし、市場やお客様に自社ないし自分自身の存在をシンクロさせた上で、自身の内なる声からでてくる「これが欲しい」「これがあるべき」というアイデアは、正解である可能性があります。
ジェームズ・ダイソンやスティーブ・ジョブズがプロダクトを生み出す裏側にあった思想は、このような「自分は何が欲しいか」「何を作りたいか」ということです。彼らは自社にできることだから作る、こういうものがあったら売れる可能性があるから作る、ということではなくて、徹底的に自分をユーザーの立場に置くことから始めます。社会やユーザーとシンクロできる立場に自分を置いたときに感じる「こういうものが欲しいのに無い」という渇望からモノを作っているわけです。そのやり方は自分の発想が基礎にあるのでプロダクトアウトではあるものの、実際は社会やユーザーの隠れた不満を押さえているというある種のマーケットインの構造にもなるわけです。もはや「マーケットインか?プロダクトアウトか?」という命題は過去のものになったのです。
大切なのはDXの“D(デジタル)”よりも“X(トランスフォーメーション)”
デジタル化された現在の社会の中で行われる活動はすべてが「DX」の色合いを帯びます。「自社としてDXにどう取り組むのか」という問いは大切ですが、現在の経営環境において何等かの企業変革に取り組むとほぼ間違いなく何らかの形でデジタル技術が関わります。また、そもそもデジタルによって変わる社会の中で行われる企業活動が、「DX」という枠組みの外となることもありません。
例えばお客様のクレームへの対応を教育するとします。通常、クレーム対応の教育がDXの取り組みと見なされることはないでしょう。しかし、今の時代にクレーム対応を考えるなら、対応を一歩間違えればSNSによってネガティブな情報が一瞬で市場に拡散したり、対応をしているその行動や会話がオンライン上で記録されていたりする可能性を教えないわけにいきません。結局のところ、デジタル化された社会におけるお客様体験を高めることを前提に教育することになるわけで、根底には「デジタル化で変わる社会」があります。ですから、現在の企業活動とは何らかの形で広義のDXの枠組みの一部と考えて差し支えないでしょう。
そう考えると大切なのは “D”よりも“X”です。デジタルという言葉に囚われる必要はありません。自社をどのように現在の社会環境に適応させていくべきなのか、ということにこそこだわるべきです。そしてその先で社会全体をどのようにより良いものに変えていくのか、そのために自社として何ができるのかを考えていかなくてはなりません。
デジタル時代における経営とはSF小説を描くこと
技術が活用された未来を想像し、活動を創造する
デジタル技術が活用された先にはどのような社会が登場するのでしょうか。それを想像することは、SF小説を書くことに近いかもしれません。
SF作品が描いているのは技術の使い方ではありません。技術が進化した先に登場する社会の姿、人間の姿です。アイザック・アシモフは「もし技術が発達して、ロボットが知能を持ったら」という仮説から、いわゆる「ロボット三原則」を打ち立てました。今、世界ではAIの活用に対して法的なガイドラインを制定する動きが盛んです。アシモフが『われはロボット(I, Robot)』の中で、ロボット三原則を表現したのは1950年ですから、実に70年前に今の社会課題を先取りしていたわけです。
岡田斗司夫さんという文化評論家の方が「日本にGAFAが生まれないのは、経営者がSFを読まないから」という評論をされています。これが事実かどうかはおいといて、技術を活用して世界をリードする企業の経営者はSFを読んでいるという考え方はなかなかおもしろいと感じます。
技術を活用するとは、技術が進んだその先にある社会の姿を想像することです。そしてその想像から、技術が生み出す正の側面と、負の側面の双方を予測して、新たな活動を生み出し、その先の価値を創造していかなくてはなりません。
自社の未来は、経営者の想像力と創造力にかかっている
経営者の皆さんは、デジタル技術をどう活用するかということ以前に、デジタル化された今の社会を考えてみましょう。社員に「DXの取り組みを行え」と指示する前に、自分自身は“DX”に自分なりの世界観を持てているのかを考えてみましょう。財務指標ばかりに目を奪われるのではなく、自社はデジタルで変わる環境下におけるステークホルダーとの関係性の在り方をマネジメントできているのかを考えてみましょう。進化する技術に飲み込まれるのではなく、技術が進化した先に登場する社会を想起し、それがより良いものとなるために自社にできることを考えてみましょう。
私たちが技術を活用する先にある社会が、例えばジョージオーウェルが描いたような、何もかもを制御された息苦しい監視社会なのか、それとも藤子不二雄が描いたような、人間臭いロボットと友達になる“少し不思議”な未来社会なのか、それは皆さんの技術への向き合い方と想像力、そしてその先にある創造力にかかっています。