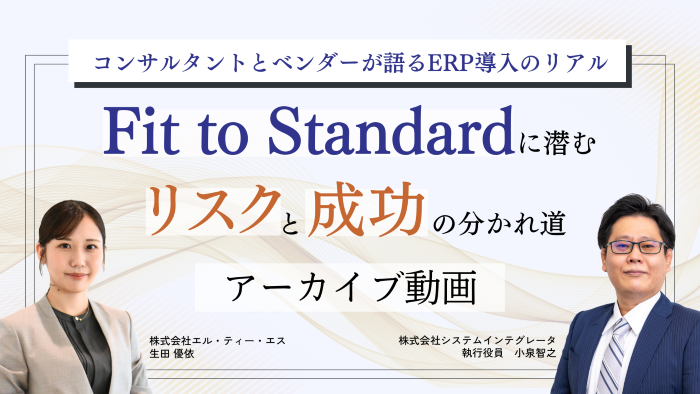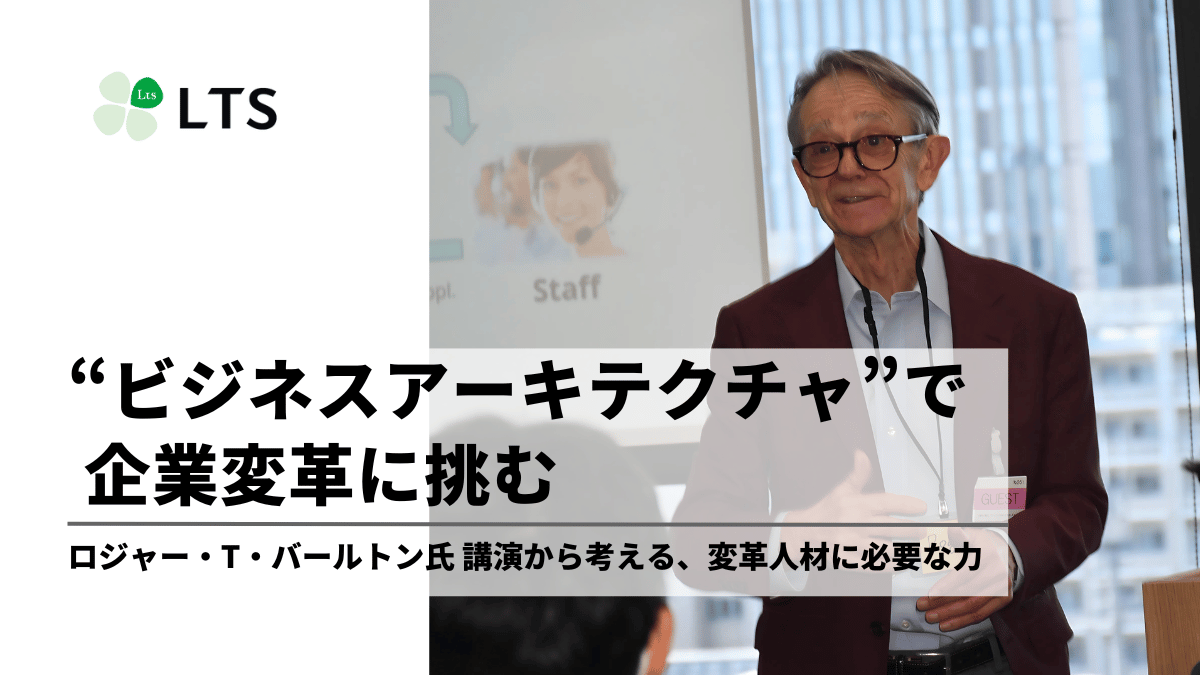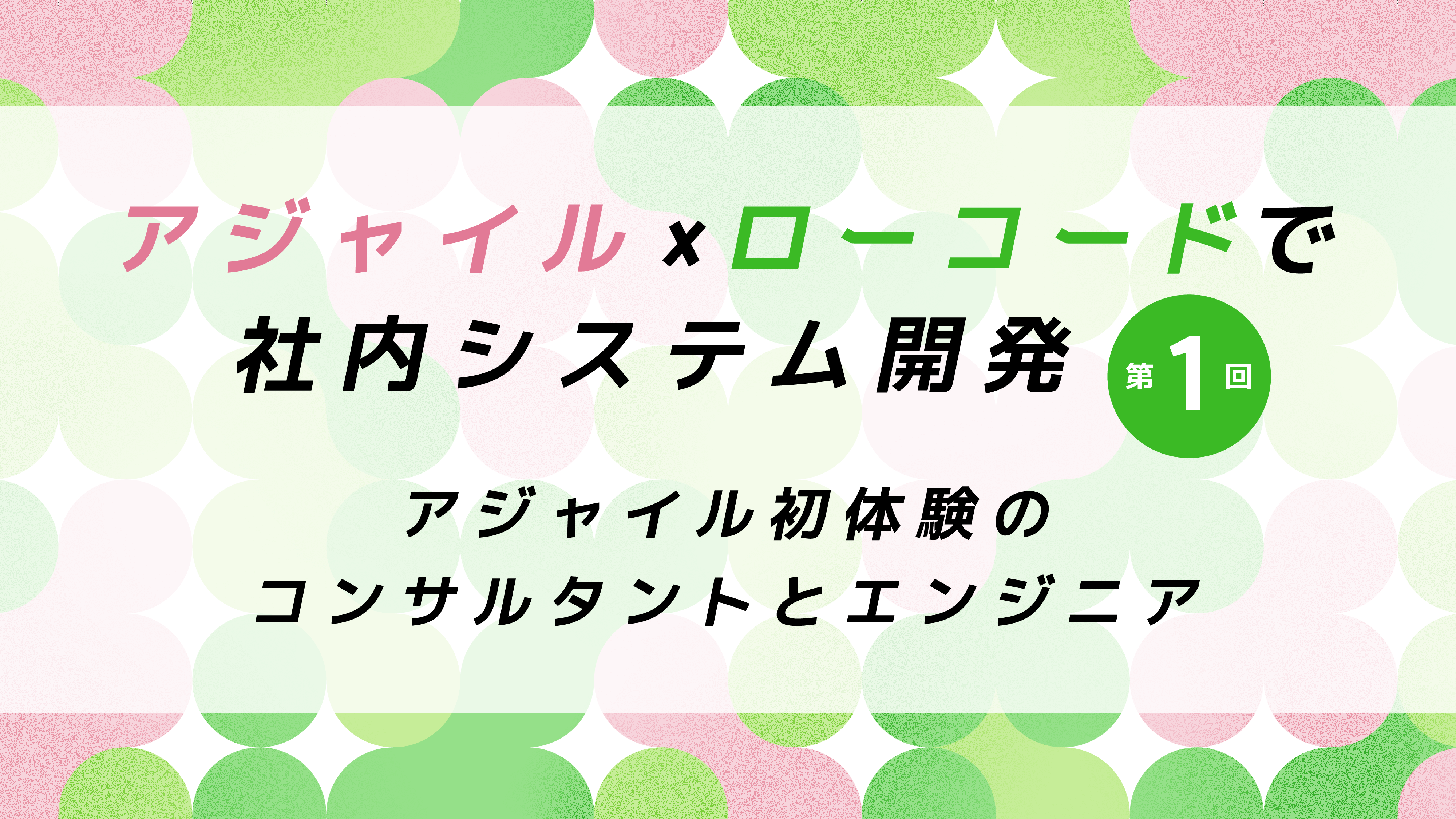ヒト、モノ、カネ、情報といった企業の資源を一元管理し業務プロセスの最適化、迅速な意思決定をサポートするERP(Enterprise Resource Planning)。その実現において 独SAP社のSAPは、世界で最も使用されているソリューションです。一方、「使いこなせるか不安」「導入は敷居が高い」との声があるのも事実です。LTSは2024年、SAPジャパン株式会社と「PartnerEdgeエンゲージメント契約」を締結し、導入や運用・保守に関するコンサルティングサービスを本格的に提供しています。本編ではLTS常務執行役員 髙橋矢が「中堅・中小企業こそSAPを導入すべき理由」を解説します。
LTS、SAP S/4HANA® Cloudの ERP導入コンサルティングサービス提供を本格開始 ~SAPと「PartnerEdgeエンゲージメント契約」を締結~
https://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-02-18-1
SaaS ERPで手に入る、シンプルで強力なDX基盤
―――SAPは大企業のためのソリューションというイメージですが、SAP社は近年、中堅・中小企業にも訴求していますね。
仰る通りSAPソリューションは大企業向けのイメージはありますが、実はこの10年は中堅・中小企業の導入が急増しており80%が中堅・中小企業のユーザーだと言われています。さらに「SAP S/4HANA Cloud Public Edition(以下、SAP Public cloud)」を軸とした「GROW with SAP」という中堅・中小企業向けのオファリングにより、短期間かつ低価格なパートナー・パッケージ・プログラムの提供を開始したことで、中堅・中小企業からの注目を更に集めるようになってきています。

―――中堅・中小企業でSAP Public cloudを導入するメリットは何ですか。
一つ目はFit to Standard(F2S)を徹底することで、業務プロセスとデータの標準化を促進できることにあると考えています。F2Sの過程で差別化領域、非差別化領域をあらためて整理し可視化できること、非差別化領域においてはSAPの標準業務プロセスを下敷きにしてゼロからでは難しい自社の業務標準を構築できることがメリットであると考えています。
二つ目は追加開発などをすることなく、最新テクノロジーを享受できることです。SAPでは年2回アップグレードがあります。例えば、最近話題になっている生成AIアシスタント「SAP Joule」は、AIエージェントが自律して人の代わりに働き業務の自動化を促進するサービスとして注目されています。非差別化領域の自動化が進むことで、中堅・中小企業の人手不足の課題に貢献する日が来るかもしれません。
三つ目は標準化された業務から高品質なデータが生成されるようになり、経営層の意思決定にこれまで以上に貢献ができることです。これらは、SAPならでは、というものではないかもしれませんがSaaS ERPの導入にチャレンジすることで、中堅・中小企業でも様々なメリットが獲得できると考えています。

一方で、SaaS ERPはその特性上、追加開発の自由度が低いため誰でも彼でもSAP Public cloudというわけではなくF2Sの合う会社、合わない会社・業界もあり、コンサルとして見極めが必要になります。仮にF2Sが合わない場合、LTSではF2Sを無理に押し付けるのではなく、業務改善方法をさらに顧客に寄り添いながら検討を進めることや、SAP以外の選択肢のご提案も行っています。
SAP導入に立ちはだかる壁とその乗り越え方
―――とはいえ、SAPは「難しい」「使いこなせない」と言われていますね。
日本企業では、例えば営業の担当者が受注業務だけでなく、発注(購買)業務も同時に担うなど、一人で複数のタスクをこなすことが多いですね。対して欧米はジョブディスクリプション(職務記述書)に基づいて役割や責任を明確化した分業が主流です。不正防止のための内部統制という意図もあります。SAPが想定する業務シナリオが、日本の商習慣に合っていないことが大きな理由の一つでしょう。

―――そうした商習慣のためか、欧米に比べ日本企業では、個別の機能を作り込んだERPを好む傾向があります。
これまではそうでしたね。日本企業では、ERPを現場のための仕組みとして導入しようとしていることに加えて、現場の声(意見)が強い傾向があります。プロジェクトの立ち上げ当初は、「ERPに業務を合わせる」という大方針が掲げられていても、現場からの圧力に押されて徐々にトーンダウンし、気が付けば作り込みだらけになってしまっていたという例は枚挙にいとまがありません。
そもそも、「業務をERPに合わせる」という方針を、掛け声を上げる側がしっかりと理解・腹落ちしていない点も大きな要因であると思います。ERPは「全体最適」を目指した仕組みです。一方、日本企業のカルチャーは「個別最適」に寄っています。カイゼンを重ねることで業績を作り込んできたのが今の日本企業です。ただし、それにも限界があります。今の時代、組織の垣根を越えて全体最適のプロセスを作り込んでいくことが必須です。カイゼンではなく最大価値を創造する業務プロセスに作り変えていくというマインドが必要です。
ちなみに、作り込みだらけになってしまうのは何もSAPだからというわけではありません。仮に国産ERPの導入であったとしても多くの個別機能の作り込みが発生してしまっている取り組みをよく見かけます。これは単純にその国産ERPの機能不足という問題もありますが、どちらかといえばF2Sのメリットを理解し、そのメリットを獲得するのだ!という姿勢の不足の問題が大きいと感じています。

―――経営者や情報システム担当者は、現場の声も無視できないこともあると思います。
基幹システムは企業の5年、10年先を支える仕組みです。従業員のハレーション対策は必要です。しかし、5年後に働いている「いまの業務を知らない従業員」を想定してみてください。「今までとこれから」のギャップはなく、それが業務の在り方であれば、摩擦もないでしょう。前述のように、その先はロボットやAIエージェントによる自動化もありますから、長期的な視野で取り組む必要があると思います。
また、企業としてこのような現場の声に正面から向き合うことは変化の激しい時代に生き残っていくためのチャレンジであるとも考えています。全社規模の大きな変革を乗り越え、変化をすることに対して自信を獲得できると、本当の意味で変化に強い企業に成長できるのだと考えています。それを支えるアプローチの一つが後にお話しするチェンジマネジメントです。

ERPプロジェクトの落とし穴—–ユーザーとベンダー、双方の課題
―――「2025年の崖」が指摘された近年、古い基幹システムの更新、新規開発のトラブルが相次いで表面化しています。原因はどこにあるのでしょう。
そもそも、基幹システム関連のプロジェクト(PJ)は、ほかのIT関連PJよりも複雑で難易度が高いものです。その上、数十年にわたって使われ改修を重ねたシステムはブラックボックス化しており、業務プロセス、システム構成、システム仕様などが最新状態で管理できておらず、自社の業務・システム・課題などを適切にベンダーに伝えることが出来ていないことが多いです。また、変革人材がユーザー企業側に不足しているという問題もあります。そういった状況の中でユーザー側としての役割を果たせず、開発・更新がベンダーに丸投げにされてしまい、トラブルに発展してしまうことがあります。

―――こういった状況の中で、トラブルを防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
ERP導入の目的をしっかりと定め、ユーザー企業が主体性を持ってやるべきことにしっかりと向き合うことが大切だと思います。取り組みの目的が定まっていないので立てられる方針にも魂がこもっていない、魂が込められていない方針は順守されない、体制上の役割・責任も曖昧になる、それぞれに割り当てられたタスクもオーナーシップが持たれない、などなど様々な問題が生じているように見えます。
また、チェンジマネジメントのアプローチを活用することも肝要です。人間は先の見えない変化を嫌う生き物です。大規模な変革は自分たちの業務や役割がどう変わるのかが不透明になることから大きな反発に繋がることが多いです。その反発から結果として過度な作り込みに繋がり、プロジェクトの難易度が上がりトラブルのリスクも高めています。現場ユーザーの変化に対する不安や喪失感などの心理的な側面に寄り添い、上手に向き合うことで、プロジェクトの目的の達成に近づけることができると考えています。
―――ベンダー側の課題はありますか。
ERPは昔から現場の業務をパッケージに合わせるというコンセプトでした。前述の日本企業のカルチャーも相まって、そのコンセプトで伴走する日本のERP導入ベンダーが少なかったのは事実です。さらに お客様の「ERPを使いこなせない」というハードルに向き合うのではなく、回避する方へ流れてしまう誘因もありました。
理由の一つは、エンジニアという性質にあるでしょう。「目の前のお客様の不便を回避して喜んでいただきたい」という心理が働くからです。逆説ですが、技術力があるほど個別最適、カスタマイズができてしまいます。もう一つは、作り込みが増えると必然的にPJの規模も大きくできるので、ベンダーとしての実績・業績に繋がりやすいということです。まさに「ベンダーの罠」ですね。
結果として顧客・ベンダー双方ともに都合のよい状態となっていたわけですが、気が付くと世界標準から取り残され、ガラパゴス化してしまいました。

―――クラウド時代に、LTSの強みはどこにあるのでしょう。
LTS創業のビジネスはチェンジマネジメントです。ですから伝統的に、ITソリューションの開発ではなく、業務プロセス改革を中心とした変革支援により企業課題の解決に伴走してきました。そのため、「ベンダーの罠」に陥らず、F2Sを実現することができます。
また、前述の通りSaaS ERPは新機能が次々にリリースされ、その機能を理解し取り入れ続けることがその価値を最大限享受することに繋がりますが、その一方でユーザー企業にとってそれは容易なことではありません。LTSはERP稼働後のお客様の小さな変革を支える伴走も積極的に行ってきました。LTSがこれまでに大事にしてきたこと、積み上げてきた経験とSAP Public cloudのコンセプトとは、親和性が非常に高く、お客様に寄り添って導入と運用を成功裏に導くことができると自負しています。「SaaS ERPといえばLTS」と認知してもらえるように強みをさらに磨いていきたいと考えています。

<「Fit to Standard」で10年後の顧客価値を最大化~LTSならではの「SAP Public cloud」導入>では、LTSのSAPコンサルタント3人による、SAP Public cloud導入のメリットやデメリット、実際の〝導入現場〟について意見交換しています。
インタビュアー・ライター

新聞記者、月刊誌編集者を経て2024年1月にLTS入社。北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニットを修了し、同大でサイエンス・ライティング講師を経験。著書、共著、編著に「頭脳対決! 棋士vs.コンピュータ」(新潮文庫)など。SF好き。お勧めは「星を継ぐもの」「宇宙の戦士」「ハーモニー」など。(2024年1月時点)